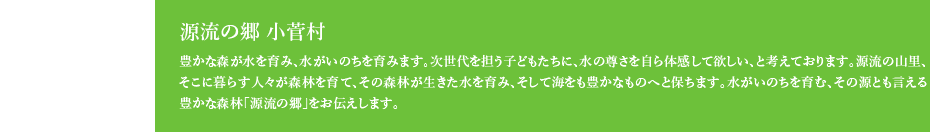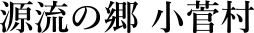村長も作る「我が家の味」
この連載の第9回で、「多摩川の最初の一滴を見に行こう」と、源流探検部が山梨県の笠取山に登った時のこと。その時、案内役を申し出て頂いたのが、多摩源流域の小菅村の舩木直美村長だった。
その日は、今にも雨が降り出しそうな夏の終わりだった。風を避けて、林の中で昼食をとることになった。歩いている時は感じなかったが、空気は湿り気を帯びていて、肌寒い。すると、舩木村長がその大きなリュックを開いた。シングルバーナーに鍋、タッパー、調理器具が次々に飛び出し、あっという間に大根の葉とミョウガの味噌汁のできあがり。冷えた身体を一瞬で温めてくれた味噌汁は、具も味噌もすべて自家製だという。
「小菅村は、今でも味噌を作っている家が多いんですよ」
源流の村の自家製の味噌が作られるところを見てみたい。その希望が、春の手前で実現することになった。
小菅村では、自家製味噌のことを「家味噌」と呼ぶ。この家味噌作りを見せてくれることになったのは、村の民宿「山水(やまみず)館」の舩木幸一さん・長子さんご夫妻だ。山水館を訪ねると、ドラム缶のかまどに乗せた大きな羽釜から、すでにもうもうと湯気が立ち上っていた。お友達でご近所さんの青柳ツヤさんと、先に豆を煮ておいてくれたようだ。長子さんは、「まあ、まずはお茶でも」と源流探検部を招き入れてくれた。まずは一緒にお茶を飲んでもてなす。これが小菅村の流儀なのだ。
左から民宿・山水館を営む舩木幸一さん・長子さんご夫妻と、家味噌作りの手伝いに駆けつけて来てくれた、ご近所に住むお友達の青柳ツヤさん。
「50年くらい前は、みんな家で味噌を作ってたんだよ」
小菅村で生まれ育った長子さんと、約半世紀前に埼玉から嫁いで来たツヤさんが懐かしそうに言い合う。
「今は一斗しか作らないけど、昔は三斗も四斗も作ったよねえ。お味噌がたくさんある家は、『おらくじん』だって言われてね。『おらくじん』っていうのは、お大尽のこと」
昔は鍋も煮物も味噌で味付けしたから、味噌さえあれば何とかなったという。
「昔は、この辺りでは醤油は買わなかったねえ。手に入りにくかったというのもあるけど、たまり醤油は味噌を作る時にできたものっていうでしょ。だから、わざわざ買わなかったんだろうね」
味噌は、村の食生活を支える調味料だったというわけだ。しかし二人は「昔の家味噌は、今みたいに美味しくなかった」と口を揃える。
「昔は米麹を入れなかったからね。ふすま麹を使っていたし、豆一斗に対して塩を一斗入れていたから、しょっぱかったね。今は米麹と麦麹を使っているし、豆一斗に対して塩は六升だから。今の方が美味しいよ」
豆一斗に対し、米麹八升、麦麹五升、塩六升。これが小菅村の一般的なレシピだ。その割合はどこもだいたい同じなのに、出来上がる味噌の味は家庭によって違うという。その理由は、二人にも分からないらしい。
味噌作りの主な材料がこちら。写真左/白い大豆と青豆と呼ばれる甘みの強い大豆。写真右/塩(上)、麦麹(左下)、米麹(右下)。
美味しさの秘訣は豆の種類と煮る時間
お茶も飲み終わったところで、いよいよ味噌作りだ。
味噌作りの工程は、大きく分けて「豆を水につける」「芯がなくなるまで煮る」「豆を潰す」「麹と塩を混ぜる」「寝かせる」の五つ。
「一日でカタをつける『日釜(ひがま)』もあるけど、かまどと羽釜で煮る時は、煮るのに5~6時間がかかるから。やっぱり暖かい方が燃しやすいから、朝から夕方まで燃しつけて、翌朝また燃しつけるの」
豆は、指で潰せるくらいまで煮るのが目安だという。実は、長子さんとツヤさんは、昨日から豆を煮ておいてくれたらしい。さらに今朝からもう一度、しっかり煮たため、豆はすでに柔らかくなっていた。長子さんが、湯気の立つ羽釜の中を指差す。
「普通の白い豆と青い豆の二種類あるでしょ。この青い豆を入れるのが大事なの。青い豆は甘くて美味しいから。食べてみて」
煮上がった二種類の豆を堂々とつまみ食いする。なるほど、味が違う。白い豆は親しみのある大豆の味がするが、青みがかった緑色の豆は、甘みが強い。
「本当だ! 甘い」と思わず声をあげると、長子さんとツヤさんが「美味しいでしょ」と嬉しそうに頷いた。
それなら全部青い豆で味噌を作ったらいいのではと思うところだが、青い豆は普通の大豆と同じ分だけ植え付けても、豆が成る確率が低く、効率が悪いらしい。そのため、普通の大豆に比べて作っている人は少ないそうだ。しかし、幸一さんと長子さん夫婦は、民宿や自宅で使う野菜をすべて作っている。もちろん青豆も作っているため、青豆を入れた味噌を作れるというわけだ。
ドラム缶のかまどにのせた羽釜でじっくり煮た大豆は指で潰せるくらい軟らかくなっている。緑がかっているのが青豆だ。
煮上がった豆をザルにあげる。この時、煮汁は捨てずにとっておくのがミソらしい。湯切りした豆は、臼に入れて杵で潰す。まずは長子さんとツヤさんが見せてくれたお手本に倣って、源流探検部の面々も杵を手にする。
二日がかりで煮てくれただけあって豆は柔らかく、杵の重みだけで潰れてペースト状になっていく。とはいえ、杵は思った以上に重く、探検部員の二の腕はすぐに悲鳴をあげた。
「昔から、これもオンナシ(女衆)の仕事。小菅ではオンナシも力仕事をしたんだよ。オトコシ(男衆)は山仕事に出て居ないから」
そう話す長子さんのそばで、幸一さんは黙々と別の作業をしている。実は、豆をすり潰してペースト状にする道具は、臼と杵の他にもある。挽肉機だ。肉の代わりに豆を入れてハンドルを回すと、豆がミンチ状になって出てくる。力はいらないが、1回でミンチにできる量が少なく、大量の豆を潰すには何度も作業をしなければならない。これはこれで、根気がいる作業だ。
みんなが疲れ始めた頃、真打ち登場とばかりに幸一さんが立ち上がった。そして手にした杵と木のしゃもじをリズミカルに操って、残っていた粒を潰してくれた。
軟らかく煮た大豆を杵と臼ですり潰すのが昔ながらのやり方だ。現在は、挽肉機を使って肉をミンチ状にするという方法もある。
買ったほうが安いと言われても自分で作りたい
臼と杵、そして挽肉機でペースト状になった豆はいくつかのポリ桶(ポリ容器の桶)に分けて入れ、桶ごとに米麹、麦麹、塩を入れて混ぜる。この時、アメを入れるのがポイントだ。アメとは豆の煮汁のこと。アメを入れると甘くなり、美味しくなるのだという。
「ポリ桶の方が早く発酵して、陶器の甕はゆっくり発酵するの。でも、甕が割れると、中の味噌は全部だめになっちゃうんだけどね」
さすがは味噌作り名人、あっという間にすべての桶で豆と麹、塩を混ぜ合わせ、一斗分の味噌の仕込みを終えてしまった。
写真左/豆の粒が残らず潰れているか確認する長子さん。右/ペースト状になった豆に、塩、麦麹、塩麹、豆の煮汁を加えていき、よく混ぜる。
「味噌作りは、三月のお彼岸から四月くらいにかけてやるもの。昔から、『味噌は土用を二つ越せばいい』って言うね。夏の土用を二回すぎると、麹が馴染んで美味しくなるってこと」
昨年の今頃仕込んだ味噌は、そろそろ食べ頃らしい。
ポリ桶の中で材料をしっかりと混ぜ合わせたら仕込み完了。このまま1年ほど寝かせて完成を待つ。味見をさせてもらうと、すでに味噌の風味が感じられた。
仕込みの後は、再びお茶の時間になった。みんなで囲むこたつには、前に仕込んでおいた家味噌と、味噌を味わうためのじゃがいも、さらにこんにゃくの煮物やヤーコンのきんぴら、ふきの煮物(きゃらぶき)、蕎麦がきまである。驚くべきは、これらはすべて、幸一さんと長子さんが素材から畑で作った、100%自家製のものだということ。
ねっとりと甘いじゃがいもに、味噌の塩気がよく合う。あまりにも美味しくて、「もっと食べて」と勧められるまま、二個目のじゃがいもに手が伸びる。
「小菅の土は、水はけがいい砂利間だからかねえ。昔から甘くて美味しいじゃがいもができるんだ。蕎麦もよくできるよ。うちは野菜でも蕎麦でも自分で作ってるでしょ。すると、『野菜なんて買った方が安いよ』って言われることもあるけど、そういうことじゃないんだ」
長子さんがしみじみと言った。ともに70代後半の長子さんとツヤさん、そして幸一さんは、エネルギーに溢れている。この小菅の自然の中で生きてきた人だからこそ、地の利を活かした作付けを生業とし、食べることの大切さを知っているのだろう。三人とおしゃべりしながら、その生命力までご馳走になったような気がした。
右から時計回りにジャガイモ、ネギを混ぜた民宿・山水館の家味噌、ふきの煮物(きゃらぶき)、ヤーコンのきんぴら、こんにゃくの煮物。すべて自家製だ。
三人と別れた後、小菅村の人に「味噌づくりを手伝わせてもらった」と話すと、「じゃあ、今度は天地返しに来てくださいね」と笑顔で言われた。天地返しとは、桶の中の味噌をかき混ぜることだという。
またひとつ、源流の村を訪れる口実が見つかった。