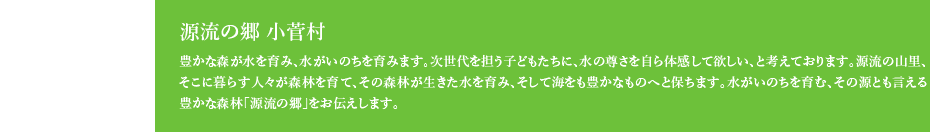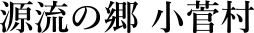ヤマメの郷・小菅村の養魚場へ
首都圏を潤す多摩川。その源流域として重要な役割を担っているのが、山梨県小菅村だ。村の95%を占める森林が育んだ水が集まって小菅川となり、多摩川へと注ぐ。
自然豊かな源流の郷・小菅村は、ヤマメの郷でもある。村の魚としてマンホールに描かれていたり、道の駅に巨大なオブジェがあったりと、ヤマメの存在は際立っている。実は、ここ小菅村は民間として日本で初めてヤマメの人工孵化に成功した土地なのだ。今も小菅村では川魚の養殖が行われており、質も高い。そのため、他県から買い付けにくる業者も多いという。
「多摩川の源流域で大切に育てられている魚が見たい!」、そう思った源流探検部は、村内の養魚場を訪ねることにした。
「悪いけど、敷地に入る前に靴を消毒してくれるかい?」
山間の木下養魚場を訪ねると、ここを営む木下稔さんがすまなそうに言った。魚を育てる上で最も怖いのは、病原菌が外から入ってくることなのだという。全員が消毒を終えると、木下さんは源流探検部を迎え入れてくれた。
川沿いにいくつも並んだコンクリート製の池をのぞくと、塊になった魚影が素早く逃げていく。春めいた日差しに照らされる水面を切り裂くように、背びれが翻る。その動きの速さに力強さを感じた。
沢の水を使ってニジマスやヤマメなどを育てている木下養魚場。小菅村の養魚場の先駆けだ。
源流が戦後の村にもたらした新しい産業
「この養魚場は、うちの親父が戦争から帰ってきた昭和20年代にできたんだ。親父は五男坊だから、仕事がなかったんだよ。だけど、お袋が総領娘だから、村から離れられなかったんだな。なぜ魚の養殖を始めたかっていうと、東京都水産試験場(奥多摩さかな養殖センター)の先生が、『小菅村は養魚にぴったりだ』って熱心に勧めてくれたからなんだ」
小菅村が魚の養殖に適している理由は、二つあるという。一つは水がきれいなこと。もう一つは水量が適量だということ。川の水が多すぎると魚が流されたりする危険がある。その点、小菅村は少なすぎず多すぎず、適量なのだという。
「その先生の指導で、うちを含めて3軒が養魚を始めたんだ。最初はニジマスだけ。当時からニジマスの餌は市販されていたんだけど、ヤマメはニジマスの餌をなかなか食わないからね。ところが、昭和30年に、この村の酒井嵓(さかいいわお)さんが、川で釣ってきたヤマメを人工孵化させることに成功したんだ」
人工孵化が成功したことで、村ではヤマメの養殖も行われるようになった。すると、この技法を学びにくる人が全国から訪れ、小菅村はヤマメの郷として知られるようになったそうだ。
父の代から始めた養殖業を引き継いだ木下養魚場を営む木下稔さん。質のいい魚を育ていることを何より大切にしている。
民間では初めてヤマメの人工孵化に成功した小菅村では、マンホールにもヤマメの姿が描かれている。
現在、木下養魚場ではニジマス、ヤマメ、イワナの3種類を育てている。取引先は河川漁協や管理釣り場、宿泊施設など。山梨県や東京都、埼玉県など、村外への出荷が9割だという。
「需要が一番多いのは、やっぱりニジマス。河川漁協の釣りの解禁が3月だから、出荷量が一番多いのは2月頃と、行楽シーズンの5月や紅葉時期。それで、需要の少ない時期に魚を育てている感じだね」
木下さんがこだわっているのは、質のいい魚を育てること。質のいい魚とはどんな魚か尋ねると、木下さんは間髪を入れずに答えてくれた。
「まず、姿がいいこと。それから、やたらとデカくしないこと」
通常、魚は個体数ではなく重量で取引される。そのため、魚を太らせ、個体数を抑えて重量を稼ぐなどの例もあるという。しかし、木下さんはそうしない。
「やっぱり、スッとしてた方が見た目もいいし、ヤマメなんかは70gくらいのサイズが一番美味しいと思うから。魚は、卵から30gにするまで6ヵ月かかるけど、30gから以降は、1ヶ月半もあれば100gになっちゃう」
だからこそ、太らせようとすることもカンタンだろう。
木下さんの育てる魚のカッコ良さは、源流探検部でもわかる。一般的に、狭い場所に魚をたくさん入れすぎると、尾びれのシルエットが丸まってしまう。しかし、木下さんが育てる魚はどれも、尾びれが凛として美しく保たれているのだ。
「魚は1週間もすればサイズが変わってしまうからね。背びれが白くなると、魚同士がぶつかっている証拠だから、すぐに別の池に移すよ」
ずらりと並ぶ池に水がしっかり行き渡るよう、木下養魚場では十分な水量を確保しているそうだ。
「イワナは水温が20度を超す日が3日続くとダメになっちゃう。夏は20度を超す日があるけど、この辺りは川の周りが木で覆われているから、上がりっぱなしにはならないんだ。大変なのは、台風の時だね」
台風が来ると、水の引き込み口に落ち葉などが溜まり、水がせき止められてしまう。水が止まれば、魚は30分で全滅する。そうならないよう、台風の日は養魚場に泊り込み、1時間おきに引き込み口の掃除をするそうだ。
「一番怖いのは、土砂崩れ。でも、今は治山・治水がしっかり整っているから、山が崩れることはないけどね」
多摩源流の水で木下さんが大切に育てたヤマメは、背びれや尾びれのシルエットがしっかり残っており、スマートで美しい。
元気な川魚を育てるための工夫と秘密
作業の様子を見せてもらった。池に入る前、木下さんは必ず冷たい消毒液に腰まで浸かる。胴長を着ているものの、まだ春浅い山では、日が隠れると寒い。
「魚を育てる上で一番気を使うのは消毒だね。他の養魚場の仕事を手伝ったら必ず自宅で風呂に入って、服も洗濯してしっかり乾かしてからでないと、ここには入らない。うちで働くスタッフが他所の養魚場に行った時は、3日はここに入らないように言っているんだ」
魚の病気を防ぐために使うのは塩だけ。薬は使わない。
それから、上空から狙って来る敵にも、気をつけなければいけない。鳥が入ってこないよう、池の周囲と上部にはネットが張り巡らされている。
木下さんは「ここは水がいいから、全部水がやってくれるんだよ」と謙遜するが、手間と愛情のかけ方は、さすがヤマメの郷の養魚場だ。
魚が病気になるのを防ぐため、池に入る前には念入りに消毒を行う。
取引先からオーダーがあったサイズのヤマメを用意するため、木下さんは池に入っていく。二つの網で魚を追い込み、箱に入れて揺する。その箱の底には格子状の枠がはめられているので、小さすぎる魚は枠から落ち、ちょうどいいサイズの魚だけを選別できる。できる限り魚に手を触れずに出荷するために工夫されているのだ。
出荷する時は、注文通りのサイズの魚種がいる池で魚を網ですくい、箱に入れる。小さい魚は水に落とされ、注文通りのサイズの魚だけが箱に残る仕組み。
池から上がった木下さんが次に向かったのは、沢に最も近い場所に作られた水槽だ。蓋を開けると、30cm四方の網が何枚も重なっている。網と網の間に見える赤い粒が、ニジマスの卵だと言う。
「直射日光を当てると卵の目がダメになっちゃうから、蓋をするんだ。この卵は、1月に採ったものだね。卵はほとんど専門業社から購入するけど、足りない分はうちにいる魚から卵を取り出して、孵化させるんだ。魚の稚魚は、湧水でないと餌付けできないんだよ。湧水の方が温かいからね。小菅村の養魚場では川の流れをそのまま利用することで、ほぼ天然の河川と同じ状況で育てていることになるよね」
沢の水を使って卵を孵化させたら、稚魚の頃から餌付けをして大切に育てていく。養魚は、水量が多すぎず少なすぎない小菅村だからこそできる産業だ。
一般的に、養魚場などで卵から孵化する確率は7~8割だという。しかし、木下養魚場では9割の卵が孵化し、さらに孵化した稚魚の9割への餌付けに成功しているという。こうした確かな技術で育てられた魚は美味しいと評判だ。実際、木下養魚場を含む小菅村出身のヤマメは、市場価格の2割増の価格で販売されている。
「釣り人は『釣りをしていると、“これは小菅のヤマメだ”とわかる』って言うんだよ」
本当かなあ、と言いつつ、木下さんの顔はほころんでいる。
「ヤマメは塩焼きも美味しいけど、70g(10cm)くらいのサイズを唐揚げにするのがオススメだね。川魚は身が淡白な分、たくさん食べられるのがいいところじゃないかな」
養魚場に土砂や雪が流入したり、病気が持ち込まれたら、大切に育てた魚はあっという間に死んでしまう。養魚は自然相手の仕事だからこそ、リスクも高い。それでも、水という自然の恵みが源流の村に養魚という産業をもたらしたのは事実だ。魚の養殖という生業もまた、人と自然の共存の一つと言える。
きれいな水で育った川魚は、これからもここが源流の郷であることを示すアイコンとして、愛されて行くことだろう。