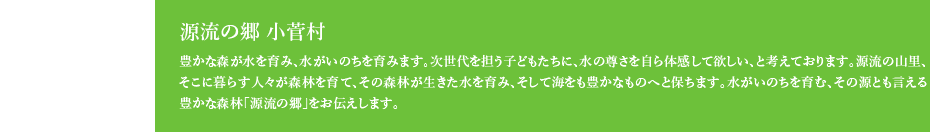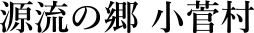源流の食文化を作った銃猟
多摩川源流域の小菅村は冬を迎えていた。降った雪は完全にはとけきらず、日陰の道で硬く凍っている。源流探検部が何度も訪れた雄滝は滝口と滝壺が凍りつき、冬だけの顔を見せてくれる。
源流の里での暮らしには、やはり都市の暮らしとは違う。その場所ならではの暮らし方や生業がある。多摩川の源流が流れる山梨県小菅村を訪れるたび、そう実感する。とりわけ強く感じたのが、小菅村の昔の水事情について、85歳の青柳一男さんを訪ねた時だ。話の途中で一男さんがこうつぶやいた。
「俺はもともと猟師だったんだ」
聞けば、20代半ばから83歳まで猟師としてこの辺りの山々を歩き回っていたという。猟のことを聞くと、一男さんの目が光った。
「そこらじゅう歩いたからな。どの山のどこにどんな木があるか、どんな岩があるか、全部わかる。昔は歩いて山に行ってたから、朝3時に家を出て山を二つ超えて、猟場に着くのは5時半頃。夜がしらじらと明けてきたら一服して、動物の足っこ(足跡)を見るわけよ。犬一、二脚、三鉄砲って言ってな。猟は犬が一番大事よ。野球のピッチャーと同じで、犬がよけりゃ、シカでもイノシシでも追い出してくれるから。犬がイノシシを止めて喧嘩するだ。その間に(鉄砲を)ぶつ(撃つ)」
一男さんは、兄弟や仲間とチームを組んで銃を使った猟をしていたそうだ。仕留めた獲物は皮を剥ぎ、骨から肉を外してから猟を行った仲間で分けた。それぞれ家で食べたり、親戚や近所の人に分けたりしたそうだ。山間部にある小菅村の人々にとって、猟は動物性タンパク質を確保するために欠かせない生業というわけだ。
「(シカとイノシシの)どっちがうめえかは好き好きだな。俺はシシ(イノシシ)。大根や玉ねぎをぶつ切りにして、シシ肉と一緒に煮る。まだよく煮えないうちに味をつけりゃ、肉が硬いだ。一時間も煮りゃあ柔らかくなるから、味をつける。味つけは味噌が一番うまい。買ってきた味噌じゃなくて家味噌。旨いど」
そう言って、恵比寿さまのような笑顔でさらに目尻を下げた。60年近く猟で歩きすぎたせいで足を悪くし、二年前に引退したという一男さん。しかし、今も猟に出た仲間のトランシーバーでのやりとりを自宅で聞いて楽しんでいるという。それほど、一男さんの人生や暮らしに猟は切っても切れないものなのだろう。
2年前まで現役の猟師として活躍していた85歳の青柳一男さん。付近の山を知り尽くす一男さんが触れているのは、20代の頃に仕留めた熊の毛皮。
多摩源流で猟を続ける現役猟師
この源流の村で、「生きること」に根ざした猟という生業をもっと知りたい。そう思って、源流探検部は現役の猟師を訪ねることにした。この連載の12回目で、現役のわな猟師の青柳博樹さんを紹介したが、今回お会いするのはわなではなく銃を使う猟師だ。
その人の名前は、青柳孝徳さん。自宅に伺うと、丸太がゴロゴロ転がっているガレージで出迎えてくれた。ちなみに、探検部が出会った小菅村の猟師は全員「青柳さん」だが、親戚というわけではないらしい。ややこしいので、孝徳さんと呼ばせてもらおう。
がっしりとした体躯に、灰色がかった瞳が印象的な孝徳さんは、現在69歳。職業は大工さんだという。孝徳さんが猟師になったのは、二十歳の時。銃猟を行うには、各都道府県の銃猟免許だけでなく、警察で銃の所持許可を受けなければならない。銃所持講習会と自分の成人式の日が重なった孝徳さんは、迷わず講習会を選んだらしい。そんな孝徳さんが行っているのは、どんな猟なのだろうか。
「日曜は猟友会の仲間と大勢で行う共猟をしますが、平日は暇な時に単独で猟をしています」
庭の犬小屋では、さっきから孝徳さんの愛犬のジャッキーが初めて見る客に警戒心をあらわに吠え続けている。
「ジャッキーは猟には連れていかないんですよ。犬にも向き不向きがあるからね。山に連れていくと、ぶどうの匂いに誘われて勝沼まで行っちゃう犬もいるから、迎えに行くのも大変でしょ」と笑った。
およそ半世紀に渡って、ここ小菅村で銃猟を行っている青柳孝徳さん。週末に猟友会の仲間と共猟するだけでなく、平日には単独猟も行なっている。
半世紀も猟を続ける理由
小菅村にはあらゆる生き物がいると言われているが、猟師が狙うのはシカとイノシシだという。熊は個体数が減っているが、シカやイノシシは増える一方だ。特にシカは1~2歳から毎年のように子供を産むため、捕獲しなければ4~5年で倍増すると言われている。しかも、樹皮や下草、新芽を食べてしまう。その結果、山が荒れて大雨による土砂崩れなどの災害の危険性が高まるため、環境省と農林水産省は261万頭いるシカ(ニホンジカ)は平成35年までに半減、88万頭いるイノシシは平成35年までに50万頭まで減らそうと目標を立てている。
小菅村を流れる小菅川。多摩川の源流域にあたるこの川で夏に源流探検部が川歩きをした時も、川原にくっきりと残されたイノシシの足跡があった。
山間に位置する小菅村でも、シカやイノシシによる被害は深刻だ。実は、孝徳さんが半世紀近く猟をしている理由もここにある。目に映るものをじっと観察するような鋭い眼で孝徳さんが言う。
「子供の頃から親父やお袋を手伝って、畑仕事をしていたんですけどね。苦労して作った畑をシカやイノシシに荒らされてきたんです。だから、シカやイノシシは敵(かたき)。でないと、こんなに真剣にできませんよ」
狩猟免許は三年に一度の更新が必要であったり、免許取得時には医師による診断書の提出も必要だという。さらに、銃の所持には厳格な決まりがある。銃と弾はそれぞれ別の部屋で、壁に固定できる鍵付きロッカーで管理しなければならない。銃や弾は決して安いものではないし、安全に気を配っていなければいけない。銃猟を行うには、手間も費用もかかるのだ。
それでも続けるのは、源流の里の暮らしや生業を守るため。探検部が孝徳さんを訪ねた数日前にも、わさび農家から役場に「わさび田にシカが入り込んでいる」と通報があり、現場に向かったという。時には、わな猟で捕らえられたシカやイノシシがなかなか絞められず、トドメを刺して欲しいと頼まれることもあるそうだ。
「シカもイノシシも夜行性だけど、たくさん食うから、昼間も食べに出てくるんですよ」
そう言って、孝徳さんが見せてくれたのが、先日仕留めたというシカの胃だ。
「シカが何を食べているのか、こっちも知っておかないといけないからね。胃の中もちゃんと調べます」
大人の腕でひと抱えほどあるタライにぴったり収まるサイズ。その中にはどんぐりを始め、わさびの葉や、村で作っている農作物などが収まっていたという。この胃を満たすには相当な量が必要なはずだ。
「シカやイノシシを撃つ時はタツマオイだ、と言われているんですよ。タツマオイってのは、立ち間(タチマ)がなまったものらしいけどね。つまり、シカやイノシシが道を渡ろうと一瞬立ち止まった時を狙え、ということ」
というのも、イノシシは時速50km、シカは時速55kmと言われるほど足が速い。だからこそ、立ち止まった一瞬を狙え、というわけだ。ちなみに、住宅街や道路、道路の法面などでの銃の発砲は禁止されているので、「シカやイノシシが渡る道」は一般的な道路のことではない。
ここで一つ、疑問が湧いた。「ここにいる」と通報がある時は別として、山の中を動き回るシカやイノシシがどこにいるか、どうやって見つけるのだろうか。
「古老から、『この山ならどこから犬が飛ぶ』と教わったりもするけど、山の中を1日歩いていりゃ、だいたい何かに出会いますよ」
けれど、闇雲に歩いているわけではないだろう。普段、猟師さんが何を見て歩いているのか、山で教えてもらうことにした。
2月の山はところどころに雪が残っているが、孝徳さんの軽トラは雪が凍った道もどんどん進んで行く。途中、軽トラが止まり、孝徳さんが車を降りた。そして、道沿いに張り巡らされた獣避けの網の下の方を指差した。見ると、針金でできた網が丸く破られている。直径およそ30cmほどだろうか。
「こんな小さい穴なんて通れないと思うでしょ? でも、シカやイノシシの子供は通っちゃうんですよ。ここは最近、何も通ってないけどね」
どうしてわかるんですか? と尋ねると、孝徳さんは破れたネットの向こうの地面を指差した。
「足跡がないでしょ」
なるほど。反対に、新しい足跡があればここを通ったということ。その足跡をたどっていけばいいのだ。けれど、雪の残る2月の山で、探検部メンバーが孝徳さんについて行ける場所は限られている。数日前にシカが入ったと通報があったわさび田に連れて行ってもらうことにした。
村内の至る所に害獣除けのネットが張り巡らされているが、シカやイノシシはそれさえ破ってしまう。破られた場所に新しい足跡がないかチェックする孝徳さん。
いざ、シカやイノシシに出会ったら、狙うべきところは決まっているという。
「正面から撃つ時は胸板、横から撃つ時は前足の付け根。そこを一瞬で撃てないと。外すと『おめえ、角見てたべ。胸板撃たねえとだめだ』って怒られるんですよ」
なぜ、胸板と前足の付け根なのだろうか。
「急所である心臓と肺と近いから。イノシシなら、横から見て腕の付け根から二寸五分(約7.5cm)に心臓があるからね」
何発も撃たずに急所を撃つことは、動物の負担を減らすことにもなるという。
「この前は、一発目は練習しちゃったけどね」
練習した=外した、ということらしい。しかし、2発目はしっかり左腕の付け根に命中し、右腕の付け根へと貫通したというから、さすがだ。
「畑に入り込んでいる時や網に絡まっている時は撃ちやすいけど、走っているシカやイノシシを撃つこともあるし、シカやイノシシがUターンしてくることもある。だから、シカやイノシシの前方と後方に人や犬がいないか、常に見ています。事故は起こしたくないからね。常に目を動かして周りを見て、仲間が犬を連れてきている時は、犬が鳴いている方向にも気を配っていますよ」
体力と集中力、知識に観察力。銃猟には、あらゆる能力が求められるのだ。
現在、小菅村で猟師免許と銃の所持資格を保持しているのは14名。最近、二名が狩猟免許を返納し、引退したそうだ。
猟師さんの数が減る一方で、シカやイノシシは増え続け、森の新芽から畑の作物まで食べまくる。猟師となって、もうすぐ50年。孝徳さんの戦いは、まだまだ終わらない。源流で生きる人々の暮らしと生業を守るために。
小菅村の特産品であるわさびは、シカやイノシシの好物の一つ。大切な農作物を害獣から守ることこそが、孝徳さんが銃猟を続ける目的でもある。