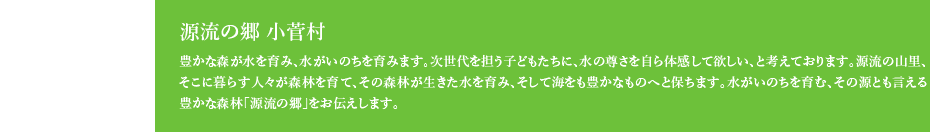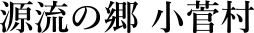戦後日本を支えた木炭は今も活躍中
多摩川源流の小菅村(山梨県)の冬。頰に当たる山の空気はきりりと引き締まっている。そんな寒さに立ち向かうように緑の葉を揺らしているのは杉や桧だ。
昔から、ここ小菅村の主要産業といえば林業だ。しかし、小菅村の林業は炭焼きが中心だったらしい。特に戦中戦後は木炭の需要が高く、昭和25年には木炭の国内消費量は200万2,708トンもあった。そのため、一大消費地と言える東京に近いここ小菅村でも、多くの人が炭を焼いていたという。
今も小菅村の山を歩くと、株立ちになった木が目に入る。株立ちとは、切り株から新芽が出て、細い木が何本も寄り集まって生えている状態のこと。炭焼きのために木を切っていた頃の名残だという。株立ちした木は日光を奪い合い、細い木は弱ってしまうが、あらかじめ間引くことで強い木を残せるという。
多摩川の源流域にある小菅村の山々は、水源かん養保安林としての機能を担ってきた。だからこそ、人が山に入り、木を切り活用することで木を強くし、そして山を守ってきたのだろう。
第18回に登場していただいた木地師の家系の亀井進さんも、小菅村の林業の代表格、炭焼きを生業にしてきた一人だ。
「戦後、木で作った製品は売れなくなってね。親父は炭を焼いていたんだ。当時は炭が売れたからね」
現在84歳の亀井さんも、若い頃からスクールバスの運転士として働きながら炭を焼いていたという。
「昔の炭焼きは大変だったよ。山の中に窯があったから、窯に着いた時に夜が明けるよう、朝3時に起きて歩いて行くんだ。あの辺りの山は東京都有林で、木を安く払い下げてもらうことができたからね」。
切った木を小菅村に運んでくるのは手間なので、木を伐り出す山場に窯を作って焼いてしまおうというわけだ。
「炭には高温でパッと焼く白炭と、低温でじっくり焼く黒炭があってね。昔は白窯って呼ばれるドーム型の窯で白炭を作ったんだ。できた炭はリヤカーや背負子で運ぶんだけど、背負子なら三俵がせいぜい。でも、頑張れば頑張っただけお金になるから、俺は五俵運んだりして、年寄りに『無理して炭が割れたらどうする』って怒られた(笑)」
ちなみに、木炭は一俵で約15kg。若かりし日の亀井青年を長老が心配したのも当然といえば当然だ。
その後、エネルギー源は石油へと変わり、木炭の需要は大きく減って行った。しかし、亀井家では今も木炭を使っている。奥さんの千江子さんが「うちのおこたは、炭を使ってるの。暖かいからあたって」と勧めてくれた。
さっそく足を入れさせてもらうと、こたつの中は全体がふんわりと暖かい。一度入ったら出たくなくなるような心地よさだ。
実は、亀井さんは定年退職後に新たに炭焼き窯を作り、今も炭焼きを行っているという。
「もうすぐ炭がなくなるから、そろそろ焼こうかな」
亀井さんのつぶやきを聞き逃さなかった源流探検部は、炭焼きを手伝わせてもらうことにした。
ヨキを自在に操る84歳の圧巻の薪割り
前日の雨が尾を引き、早朝に濃霧が立ち込めた冬の日。村を見下ろす高台に作られた炭焼き窯を訪ねると、亀井さんは窯の中に残っていた炭のかけらを掃き出していた。窯は、亀井さんが自分で作ったものだという。
「昔焼いていたのは白炭だけど、これは黒炭を焼く窯。黒炭は火を起こしやすいから、今は黒炭しか作らないんだ」
自宅で使う分だけ焼けばいいので、窯の大きさは小ぶりだ。それでも、1回の炭焼きには20mの長さの木が三本は必要だという。材料となる木も、亀井さんが用意してくれていた。
亀井さんが自分で作った炭焼き窯。ここで黒炭と呼ばれる炭を焼いている。窯の中をのぞくと、奥に排気口が作られていた。
「この辺りでは、炭にするならナラの木だね。でも、それだけじゃ足りないから、いろんな木を使うよ。使うのは生の木の方がいいね。乾いた木は燃えすぎるから」
今回使うのはナラの木とクリの木だ。山から切ってきた木を1mほどの長さに玉切ってから、さらにヨキで薪割りして使う。亀井さんは自在にヨキを操り、硬いクリの木をパカーン、パカーンとリズミカルに切り分けていく。
「ナラの木とクリの木は似ているけど、割ると分かる。クリの木は目がまっすぐに走っていて、きれいに割れるんだ」
それなら、と探検部もクリの木の薪割りに挑戦してみたが、重いヨキを狙ったところに振り下ろすのも、力を込めて振り抜くのも難しい。「上腕が 明日はきっと 筋肉痛」と心の中で五・七・五を唱えながらヨキを振り下ろしていくうちになんとか薪割りが完了した。
まるで包丁で野菜を刻むかのように、サクサクと薪を割っていく亀井さん。源流探検部メンバーは重いヨキを木に当てるだけでも一苦労だ。
まるでパズル! 狭い窯で薪と格闘
薪の準備ができたら、炭焼きの工程の始まりだ。まずは窯の中の床に鉄の棒を並べ、その上に鉄の網を乗せる。そして、その上に薪を立てて並べていくのだ。窯の奥には空気穴が開いているため、床を底上げすることで空気と火が循環しやすくなるのだという。
窯の中に入ると、外から見ていた以上に狭い。中腰になって薪を一本一本並べるのは、かなりの重労働だ。隙間ができると木が燃えすぎていい炭にならないので、パズルのように薪を組み合わせていく。窯の中は暗いので、ほとんど手探りだ。時々、足で薪を押してさらに隙間をなくす。ある程度並べたら、今度は立てて並べた薪の上に木を積んでいく。
「天井に近いところは燃えやすいから、燃えてもいい木を置くんだよ」
ここでも隙間ができないよう、短くて立てかけられない薪や細い枝をパズルのように組み合わせ、隙間なく並べていく。伐った木を余すことなく使うのだ。入り口付近には燃えやすい木や燃えてもいい木、さらには木っ端も総動員して、「これ以上、入らない!」というところまで隙間なく並べた。
一定の長さに揃えた薪を並べ、その上には短い薪や細い枝を詰めていく。隙間ができると燃えすぎてしまうので、隙間なく並べるのが炭焼きのポイント。
ここで亀井さんが取り出したのが、二つのレンガだ。入口の穴に二つのレンガを山型に置き、その上に石と粘土を隙間なく重ね、入口の上半分だけ蓋をする。この粘土は小菅村の山で取れる粘土質の土に水を混ぜたもの。炭焼きのたびにリサイクルして使うそうだ。
窯の入口の上半分を粘土で塞ぐと、いよいよ火入れだ。窯の入り口の空いているところから、木っ端に火をつける。オレンジ色の火はゆっくりと木を登りながら勢いを増してゆく。奥まで火が広がっていくまでには時間がかかる。その間に、手前の木が炭化してこぼれ落ちてゆく。
「こういうのがパチンと爆ぜて飛んでいくと危ないんだ」
そう言うと、亀井さんは入り口に溜まった細かい炭をシャベルですくい、ドラム缶の中に入れた。
薪全体に火が回ったかどうかは、煙の色で確認すると言う。
「始めは白い煙、次に青い煙がでて、最後は煙が出なくなる」
しかし、しばらく使っていなかった窯はなかなか温まらず、煙が出てこない。その間に、冬の太陽は足早に山の稜線を滑り降りてゆく。
後ろ髪を引かれながら東京に戻った探検部の元に「無事に窯に火が回った」と連絡が入ったのは数日後のことだった。炭は三日間かけてじっくり焼かれ、1週間かけてゆっくりと冷まされていった。
窯に薪をぎっしり詰め込んだら、レンガ・石・粘土を隙間なく重ねて蓋をする。ここで使う粘土は小菅の村の土を炭焼きのたびに繰り返し使う。入り口の上半分がふさがったら、窯の木に火をつける。
ついに完成! 100%地元の材料で作った木炭
改めて亀井さんを訪ねると、すっかり冷めた窯の中では出来上がった炭が取り出されるのを待っていた。
窯の入り口いっぱいに詰めたはずの薪は、木炭になると4分の3ほどの量に減っていた。薪と薪の隙間が多いと空気が入りすぎて燃えてしまい、量が減るらしい。きっと、炭焼き初心者の探検部の並べ方が甘かったのだろう。それでも、窯の中から早く木炭を取り出して見てみたい。亀井さんに入り口付近の「燃えてもいい木」を鉤のような棒で取り出してもらって、窯の中に入った。
狭い窯の中で、木炭に手を伸ばし、一本一本取り出していく。窯に入れた薪の重さを思い出し、木炭の軽さに驚く。窯の入り口にぶつけて割ってしまったり、ちょっと強くつかんだだけで崩れてしまうものもある。特別に硬くて重い木炭は、きっとナラの木だろう。
出来上がった炭を見て、亀井さんが笑った。
「これで焼き鳥を焼くと、旨いんだ」
崩れて小さくなった木炭もバーベキューに使ったりと無駄にはしない。しかし、木炭中には根元が炭化しきらなかったものもある。しっかり炭になっていないものを燃やすと煙が出てしまうので、のこぎりで切り落とす。
完成した木炭。源流探検部が窯に薪を並べた時に隙間ができたせいか、質量は大幅に減っていたが、炭になっていた。
根元が炭化しきらなかったものは、のこぎりで切り落とす。
「ちょっと休憩しようか」
亀井さんが、秘密基地と呼んでいる小屋のストーブに、できたばかりの木炭を足す。ストーブの上では、亀井さんが焼いておいてくれた焼き芋がちょうど食べごろになっている。石焼き芋ならぬ、炭焼き芋はねっとりと甘かった。
真っ赤に燃えた炭の美しさに見惚れ、その暖かさに癒される。けれど、木炭は単なる燃料ではない。水質浄化や空気浄化、土壌改良とさまざまな可能性を秘めているのだ。その土地の土を使って窯を作り、その土地の木の命をいただいて木炭を作る。炭焼きもまた、山の豊かさとともに生きる源流文化の一つなのだと実感した。