

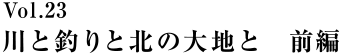

大雪山系の三国山に源流を発し、北見盆地を北流してオホーツク海に流れ込む幹川流路延長120kmの一級河川。並行して流れる最大支流の無加(むか)川とは北見市中心街で合わさる。本流は濁りが強いが、透明度の高い支流が幾本も流れ込み、夏から冬にかけてはオホーツク海よりサクラマス、カラフトマス、サケが遡上する。秋、下流域にはこれらの魚を漁獲するためのウライ(一括採捕用の罠)が設けられるが、水位が上がると魚たちはこれを越え、本流や支流で自然産卵を行う。
冷え込んだ朝、とある小さな支流へ
山内さんはウエーダーに足を通しながら、ようやく訪れた秋の朝の冷え込みを喜ぶかのようにつぶやいた。いまだ真夏日の続く埼玉南部から北の大地まで一気に緯度を上げた私は、季節の大きな分かれ目に立ち会った気になっていた。ひやっとした空気の湿り気と、広葉樹のほの甘い香り。斜面を下ると、森のトンネルの向こうへと延びる小さな流れがあった。くぐもるせせらぎを聞くと、気持ちが一気に昂ってきた。
「例年なら今頃がピークなんですけどね」と山内さん。「まだいるといいんだけど……」
木々のトンネルを抜け樹冠が開けたところで歩を止めた。用心深く身をかがめ、そろりそろりと前へ進む。私は5mほど後方に留まり、山内さんの様子を伺う。腹這いになり、ほとんど匍匐前進で川辺に近づくと、こちらを振り向いた。どうやらいるようだ。背後の土手に背中を押しつけるようにしてカニ歩きで近づくと、灰色と赤紫色が混ざり合わさったような背の盛り上がった魚が数匹、緩やかな流れの中に並んでいた。上流下流に目を送ると、あちこちで流れを分ける背が見える。
「今年一番の数でしょう。最高のタイミングに当たりましたね」
前方の一匹が体を横たえると真っ白い腹が露わになった。水面に泡をかみながら川床をかき混ぜ、ドシャドシャドシャと力強い音を立てる。30年ぶりに見る姿に、私は胸を熱くした。

ここは道東、オホーツク海に注ぐ常呂川の小さな支流。幹川流路延長120kmの一級河川である常呂川は、南北に細長く開けた北見盆地を貫流し、北海道で最も広い市である北見市と隣接する置戸町、訓子府町に広げた支流から水を集める。そしてこの時期、常呂川には北の海で成長したサケやマスたちが産卵のために戻ってくる。




常呂川は北見市の中心街で最大支流の無加川と分かれ、これより上流は大雪山系に向かって2本の本支流が並走して流れる。無加川が貫流する北見市留辺蘂(るべしべ)町には、歴史のあるおんねゆ温泉郷、そして淡水魚専門の水族館として日本最北の「北の大地の水族館」がある。趣向を凝らした滝つぼ水槽、四季の水槽、そして1mオーバーの巨大魚・イトウを展示する北見市の目玉施設だ。そして当水族館の館長が、今回お世話になった山内創さんだ。

一日中でも見ていられるカラフトマスの産卵行動
山内さんと肩を並べ、カラフトマスの産卵行動を観察する。すぐ目に付いたのは、産卵床を掘る45cmほどのメスと、その下流側に付き添う一回り大型のオスだ。水面上に迫り上がった背中が目を引いた。
サケやマスの仲間は海から川に遡上すると独自の婚姻色に身を染めていくが、カラフトマスは黒ずんだグレーの背中に白いお腹とモノトーンで、他のサケマスに比べて派手さはない。代わりにオスの背中がうちわのように盛り上がり、アゴが伸長してカギ状に曲がる。その風貌はまるで、原始的な小型肉食恐竜のようだ。


寄り添うペアの後方には、さらにオスが2匹。メスに近づこうとしてはペアのオスに鼻面で押され、阻まれている。メスは横たえた体を波打たせては河床に並んだこぶし大の石の間に溜まった砂を洗い流しているように見える。たびたび川底にお腹を押し付けては石と石の隙間に尻ビレを差し込み、なにかを探っているようなそぶりを見せる。そのたびに3匹のオスはギュッと緊張して、メスに近づこうとする。どうやら産卵の瞬間が近いらしい。「これは…‥今にも産みそうですね」と山内さん。
山内さんとはこれまでもSNSを通じてやりとりがあり、サケやマスの産卵行動に通じていることは知っていた。水族館勤めだから飼育のプロであることは当たり前だが、フィールドにも足繁く通っては、季節ごとの生きものを相手に趣味の観察や撮影を楽しんでいるという。改めてともに同じ魚を観察することで、山内さんの豊富な経験に基づく視点を借りて楽しみが広がっていく。

目の前のメスはもうだいぶ掘り起こし行動を続けているようで、長径1mほどの楕円形をした産卵床が、河床に明るく浮かび上がっている。赤、青、白、薄桃色……メスに磨かれた河床の石は色とりどりで実に美しい。大袈裟ではなく、まるで川底に宝石を散りばめたようだ。「赤い石は赤チャート、青い石は青チャートと呼ばれています。この川は特に川底の石がきれいなんですよね。石があまり丸くならずに角張っているのも特徴です」と山内さん。サケの一生を描いた『ピリカ、おかあさんへの旅』という大好きな絵本がある。河床の石が実に鮮やかに描かれているのだが、フィクションとばかり思っていた風景が目の前にあった。季節は秋のはじめ、頭に「石紅葉」というフレーズが思い浮かんだ。

しばらく観察を続けていると、少しずつ目の前の魚たちの関係性が知れてくる。産卵床を守るペアのオスとメスがいて、その後方にはメスを狙うオスが2匹。このほかに、対岸と上流側に、それぞれ1mずつ離れた位置に別のメスが単独で産卵床を掘っている。これらのメスが時折、思い立ったようにペアのメスに猛然と噛み付いてくる。力の均衡したオス同士の争いも激しいが、しつこいのはメスの方だ。自ら卵を産む産卵床をつくるメスは、オス以上に場所への執着が強いのだろうか。他のメスが自分のテリトリーに入ると猛然と追い払い、その勢いで相手のテリトリーに入ってしまうと逆に追い払われ、行ったり来たりを繰り返している。
ちょうど30年前となる1994年、私はオホーツク海から遡上するサケとカラフトマスの産卵行動を8mmビデオに記録していた。水産大学の卒業論文に選んだテーマは「繁殖行動中におけるシロザケの同種・異種への攻撃行動」。川の瀬を真っ黒に覆うほどのカラフトマスの大遡上を目の当たりにして、ただただ、その数に圧倒されたことを思い出す。この時以来、サケやマスのことを常に気にかける人生を歩むことになった。
メスがちょんちょんと反らせた腹の先にある臀ビレで卵を産む場所の具合を確かめる。いよいよ産卵の瞬間が訪れそうな雰囲気が高まった。……と、その時、上流側から場違いのような大型のサケが現れた。ふらふらと体を揺らしながら頭を上流側に向けたまま流れを下り、ついにカラフトマスがつくった産卵床の上に落ち着いてしまった。敵に回すにはあまりにも巨大な相手にもかかわらず、カラフトマスのメスは果敢に噛み付いていく。「いつも思うんですけど、サケが来てもオスのカラフトマスはあまり攻撃しないんですよね。どちらかというとメスは相手がサケだろうと一生懸命排除するように思います」と山内さん。しばらく静観していた(?)ペアのオスも重い腰を上げるようにサケとメスとの間に入流。盛り上がった背中をサケの頭に当てて、少しずつ下流へ押し出していく。だがサケとの間にわずかな距離が生じた瞬間、ものすごい勢いでサケがカラフトマスのオスの体に噛み付いた。噛まれたオスも負けじと噛み返す。「いけっ!」「がんばれ!」「……ああっ!」「負けるな!」
手に汗握る瞬間の連続に、山内さんと二人で演者の魚たちに声を掛け合う。迫真の生ライブ。テレビなどでは口を開けた産卵の瞬間がドラマチックなシーンとして切り取られがちだが、より面白いのはそこに至るまでの一連にありますよね、と意見が合った。
「これ見ていたら、1日があっという間に終わってしまいますよね」
あまりにもサケが産卵床に長く居座り続けるものだから、メスはすっかりやる気をなくしたのか、下流に下がってしまった。

夢中になっている間にずいぶんと雲が湧いてきた。川を通る風が心地よい。ふと、山内さんが空を見上げ、声を上げた。「オジロワシです!」
私が気づいた時にはすでに随分と空高くを舞っていたが、それでも大きさは見てとれる。私たちのいる少し下流から飛び立ったようだ。山内さんが言うには、産卵に上がってくるサケやマスを食べにくるのだという。私たちの声が気になって川を離れてしまったのかも知れない。「羽を広げると2mほどはありますからね。釣り人の友だちがすぐ背後にいたオジロワシを見て『ペンギンだ!』って呼んだことがあります(笑)」
さらにその後、ハトよりも大きな鳥が川をまっすぐ上流に向かい、直角に曲がって山向こうへ飛び去った。ヤマセミだった。「これは素晴らしい1日になりましたね」と山内さん。コココココ……。コココココ……。森からは派手なキツツキのドラミングも聞こえてくる。クマゲラも普通に暮らしている土地なのだということを教えてもらう。
気づくと立ちっぱなしで、もう3時間半も経っていた。随分前にサケは去り、メスは掘り返しを再開していたが、気分を害したのか、掘る場所が定まらない。
「……疲れましたね(笑)」と山内さん。
「もう一度、あのサケが戻ってきたら、あきらめて移動しましょう」と私。
そしてようやくメスがやる気を見せ始めた頃、お約束のように下流から水面に引き波を立ててあのサケが帰ってきた。脳内に映画「ジョーズ」のBGMが流れたところで一区切り。産卵の瞬間を見ることは諦め、下流へ下ることにした。

移動するとすぐにカラフトマスのホッチャレを見つけた。ホッチャレとは産卵後の死骸のこと。サケやカラフトマスは産卵を終えると命が尽きる。死骸はそのまま河辺に残され、キツネやクマ、オオワシやオジロワシの餌になる。食われずに残った部位は朽ちて川の栄養となる。海で蓄えた栄養分を運ぶことから、「Salmon make a forest(サケは森をつくる)」ということわざもあるほどだ。


山内さんが岸辺にずり上げられたメスの死骸を見つけた。目玉だけを失った魚は、さっきまで生きていたのではないかと思えるほど新鮮だ。「オジロワシだと思います。鳥は目が大好物ですから」。山内さんは指で魚の腹を押して確認すると、川に目を移してこう言った。「もしかするとこの産卵床を掘っていたメスかもしれません。お腹にはもう卵が残っていませんでしたから、産卵を終えて弱っていたやつかもしれません」。
尻尾は擦り切れ、尾骨が露わになっている。生涯一度の産卵のために最後の力を振り絞るカラフトマスの姿に改めて心を打たれた。
「卵がびっしり詰まった状態で食べられているやつもいます。海を延々と長旅して、さあこれから産むぞという時に……。どうしても魚目線で考えてしまいますよね」と山内さん。


カラフトマスの死骸を戻し、さらに川を下ると合流部に出た。常呂川本流だ。工事か何かの影響かと思うほど、ひどく濁っているが、常にこの水色なのだという。この支流まで常呂川本流には魚の遡上を妨げる堰堤がない。唯一の障壁は下流域に設置された「ウライ」と呼ばれる一括採捕罠だ。ウライで漁獲されたサケやカラフトマスから採られた卵は、人工孵化放流のために用いられる。ただ、ウライの柵は少し増水すれば水没する高さにとどめられているという。河畔林が刈られ、開けた川辺を歩きながら山内さんが言う。
「6年ほど前には本流のここら辺にも数えきれないほどカラフトマスの産卵床がつくられた年がありました。支流にもすごい数が。今日の10倍はいたと思います」



カラフトマスは日本から去ってしまうのか?
ちょうどこの日の前日に、令和6年8月31日までのカラフトマス来遊状況が発表された。その数3万5千尾で、前年同期比52%、平年同期比は実に1%。平成元年(1989年)以降で最も少ない数だという。太平洋の海水温が著しく高まる「海洋熱波」が主な原因とされていて、ここ2、3年は「最後のひとしずく」とも呼びたくなるほどの激減だ。この影響は、山内さんが館長を務める北の大地の水族館にもおよんでいる。季節に応じた魚を展示する「四季の水槽」では、例年9月初旬にはカラフトマスの展示を始めるが、今年はまだ展示できていないという。「カラフトマスは見た目もかっこいい魚ですから、楽しみにしてくれるお客さんも多いのですが、残念です」と山内さん。
ただカラフトマスの減少は、日本に限った話でもあるようだ。皮肉にも全世界で見ると、カラフトマスは今、過去に例を見ないほど数が増えている。温暖化の影響は、日本近海からカラフトマスを去らせると同時に、より北方にはカラフトマスの暮らしやすい海域を広げているという。
「たぶん、一人一人にできることってないに等しいと思うんです。大好きな魚なので寂しいし、なんとかしたい思いも当然あります。私にできることは実際に見にいって現状がどうなっているのかを感じながら写真や動画を残したり、水族館で展示してお客さんに知ってもらうことなのかなと考えています」



お昼休憩を挟んで再度、支流に戻ってきた。ドライスーツを着込み、水中カメラを手に川へ下る。カラフトマスたちの配列に変化はないように思えたが、産卵床の形が変わっていた。どうやら我々が席を外している間に産卵したらしい。山内さんはゴーグルを着けると、静かに水辺へと近づき、まるで液体のように川に滑り込んでいった。




