ヒラメ釣りに必要な感度と操作性を徹底的に追求。
活き餌を泳がせるヒラメ釣りでは、活餌の状態やヒラメの食い込み具合がわかる感度、底立ちや誘いがスムーズに行える操作性が釣果に直結する。
しなやかながら、高感度を誇る『SMT』を穂先部に採用。ガイドにはRタイプフレームとNリングを組み合わせた『AGS』を採用し、軽量化と穂先のブレを軽減。
SVFナノプラスを使用したブランクはX45で補強することでねじれを防止、大判ヒラメや不意の青物にも釣り人が主導権を握ったファイトが可能に。
そしてESS&新バランス理論を駆使し、しなやかさと操作性という相反する要素が絶妙なバランスで両立する調子を実現している。
イメージ通りに活き餌を操作し、狙ったヒラメを掛け逃さない理想のヒラメ竿が誕生。
※前作との比較
MH243:SMT部のショート化で、圧倒的な感度と操作性を獲得
S/MH272:よりしなやかな穂先を採用し、ヒラメに違和感を与えずオートマチックに食わせる調子に進化
SS/MH-245:ヒラメ竿最軽量クラス 109g。食い込みと目感度に優れた極軟穂先と、強靭なバットパワーが融合した新調子”フレキシブルパワーモデル”
極鋭ヒラメ EXKYOKUEI HIRAME EX
ヒラメ竿最軽量クラス!ヒラメ釣りに必要な感度と操作性を徹底的に追求
ダイワテクノロジー

感性領域設計システム [ESS](エキスパートセンスシミュレーション)
ロッドは曲がると、その方向と反対側に起きあがろうとするエネルギー(復元力)が発生します。これは、変形した(ひずんだ)ブランクが元に戻ろうとする「ひずみエネルギー」であり、竿の性能を左右する極めて重要な要素と言えます。DAIWAは「ひずみエネルギー」を解析・設計するシステムを独自に開発し「どこが優れているか」「どこが足りないか」を数値で明確に把握するだけでなく、釣り人がもつ感性の領域をも設計に反映する事が可能となり、より釣り人が求めるロッドへと近づいていきます。
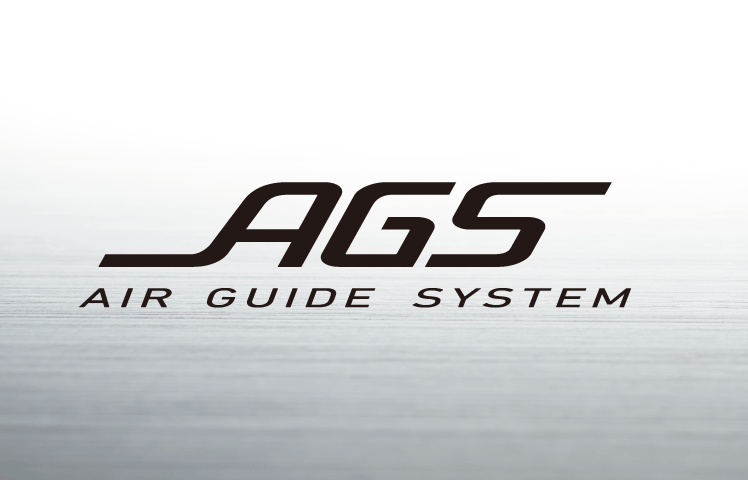
AGS
軽量・高感度を実現するAGS(エアガイドシステム)はカーボンフレームを採用しており、チタンと比較して約3倍の剛性をもつカーボンの特性から、ラインを通して伝わるわずかな信号を吸収することなくダイレクトにブランクに伝える高感度を有します。また、カーボンの軽量性によりロッド全体の軽量化にも貢献し、特に穂先部の軽量化につながることで感度の向上にも追加の効果が見込めます。

AIR SENSOR SEAT
カーボンファイバーの入ったエアセンサーシートにより、軽量化・高強度・高感度を実現します。ロッドの用途に応じて専用設計がなされており、汎用リールシートでは体験できない操作性をもたらします。
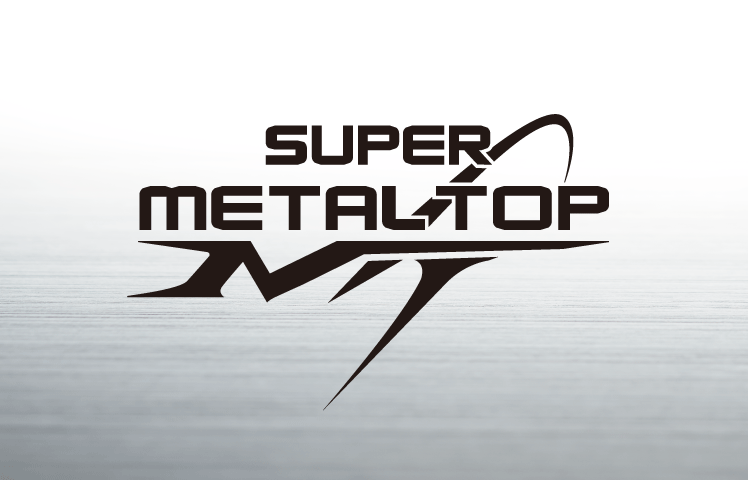
SMT(SuperMetalTop)
SMT(スーパーメタルトップ)とは、超弾性チタン合金素材をロッドの穂先に使用したDAIWA独自のテクノロジー。金属ならではの振動の増幅力から、カーボン素材では不可能な領域の感度を釣り人に提供します。弾性の高い金属素材の特徴である強度と外傷への強さに加え、わずかな動きにもしなやかに曲がる繊細な穂先を実現できることから、アタリを手元までしっかりと届ける金属ならではの手感度と目に見えるアタリの目感度に優れています。

SVF NANOPLUS
軽さ・パワー・細身化を実現する超高密度カーボンSVFに東レ(株)ナノアロイテクノロジーをDAIWA独自の製法で組み合わせ、さらなる高強度化・軽量化を可能としました。

X45
キャスティング、アクション、フッキング、ファイトなどの動作の中で発生するネジレを防ぐため、長年の研究によりネジレ防止の為には従来構造(竿先に対して0°、90°)に加え「45°」のバイアスクロス(±45°に斜行したカーボン繊維等)を巻くことが最適であるとの結論に至りました。X45の搭載により、ネジレを防止し、パワー・操作性・感度の飛躍的な向上を実現しました。
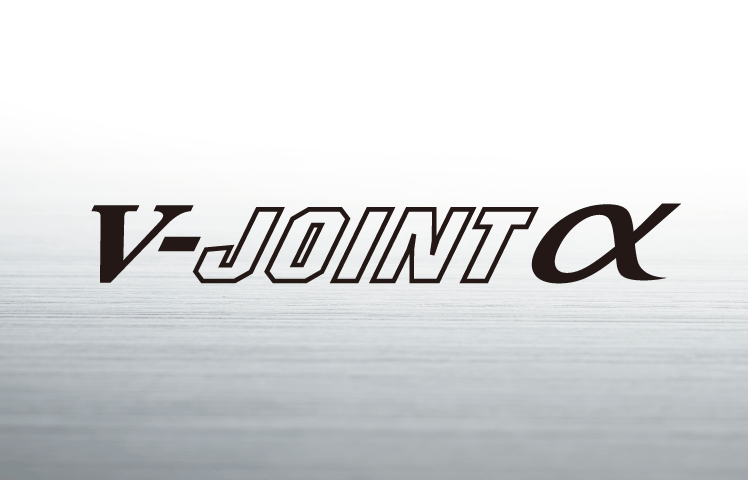
V-JOINTα
ジョイント部に高強度素材のナノアロイを採用し、DAIWA独自の精密加工技術を駆使することによりV-ジョイントαは誕生し、V-JOINTをさらに強く・軽く・きれいな曲がりへと進化させました。継ぎ数の多い竿では、ジョイント部を短くすることが可能になり、強さを実現しつつ軽さの実現に寄与します。
製品詳細

■薄肉・軽量のC、Nリング
軽量・高剛性・トラブルレスのRタイプフレームと、新開発薄肉・軽量のNリングを搭載。

■『SMT』搭載
感度と強度に優れ、活性の低い居食いのような繊細なアタリも表現してくれる。

■SS/MH-245 :『SMT』特徴
SS/MH-245 のSMTは、これまでのノーマルヒラメ竿と比較し異質とも呼べるほどしなやかにチューニング。食い込みと目感度に優れた極軟穂先。

■エアセンサーシート
リールシートに最適な軽さと高剛性、高強度を追求したカーボン強化樹脂採用。軽さと剛性の両立により感度に優れたエアセンサーシート(スリムフィット)。

■さりげないナットへの「EX」印字が高級感を演出
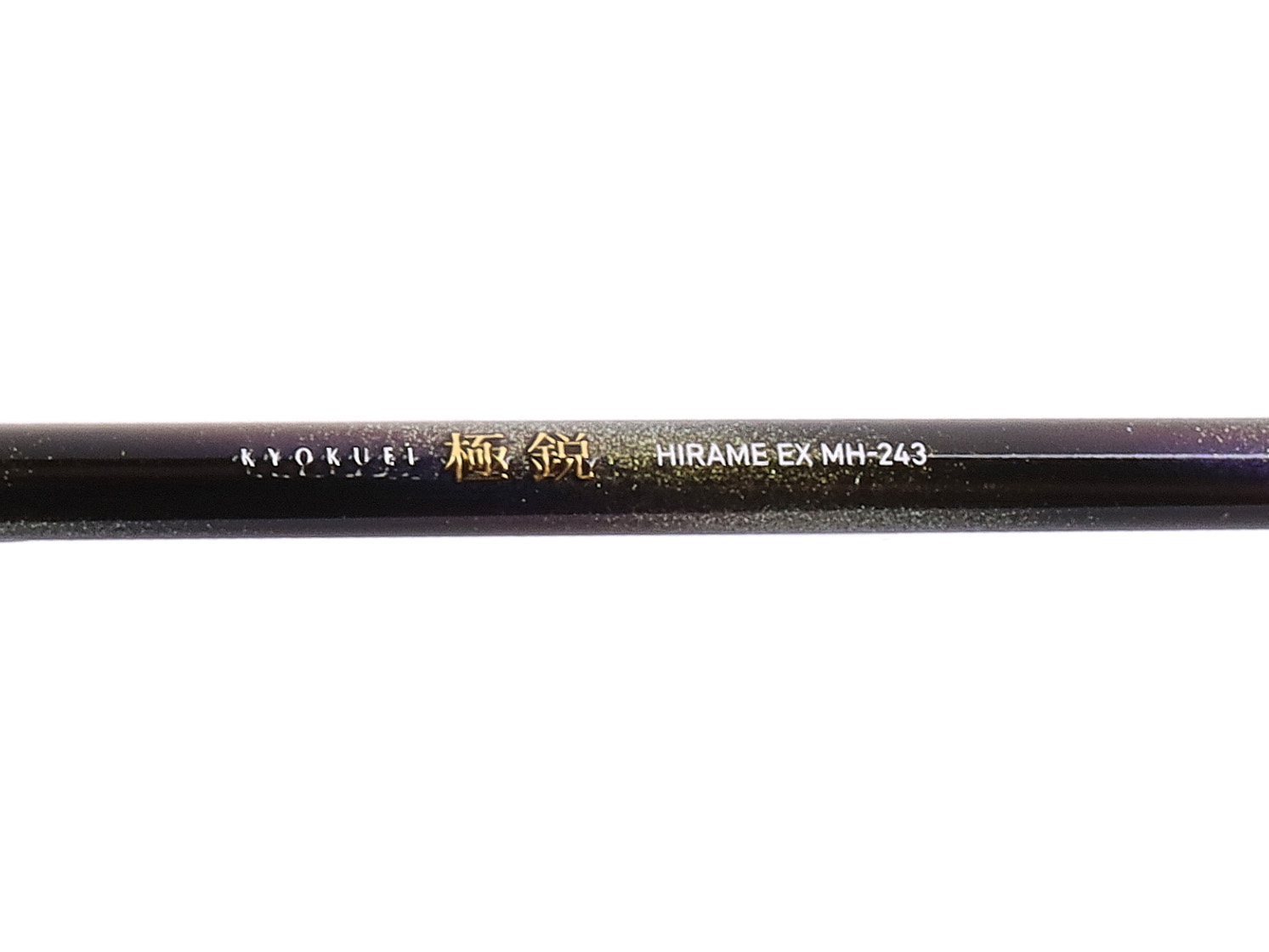
■光輝性に優れた立体ネーム部

■パッケージ

■リールシートと竿本体に偏光色を採用。太陽の高さや光量によって色調が変化。
| アイテム | 説明 |
|---|---|
| MH243 | 手持ちに最適で操作性が際立つ”軽快ショートモデル” |
| S/MH272 | しなやかな穂先を採用し、置き竿でも違和感なく食わせる”オールラウンドモデル” |
| SS/MH-245 | 食い込みと目感度に優れた極軟穂先と、強靭なバットパワーが融合した新調子”フレキシブルパワーモデル” |
左にスクロール
右にスクロール
MOVIE
テスターインプレッション

福田豊起テスター ⅯH-243
ヒラメ釣りのどの場面においてもロッドの感度は手感度、目感度共に非常に重要な要素だ。その感度に大きな一石を投じたのが先代の極鋭ヒラメEXだ。初めて極鋭ヒラメEXをテストした第一投目の感度は衝撃的で、今でも忘れることは無い。オモリが海底を叩く感覚が今までのロッドとは別次元と感じたものだ。さらに実釣を重ねるにつれ、極鋭ヒラメEXの感度をもとにイメージを積み上げていく釣りの楽しさにハマってしまい、極鋭ヒラメEXでないと物足りないとまで思うようになってしまった。このブレイクスルーは極限まで贅肉を削ったカーボンマテリアルであるSVFナノプラスと次世代AGSによってはじめて実現されたものであった。
この後、数年を経て私の注目する新しいDAIWAテクノロジーが生まれた。その名も『新バランス理論』。しなやかさと操作性という、一見相反する要素を高次元で両立する新しい設計思想だ。この『新バランス理論』であるが、船ロッドを一新させる可能性があることを私はたびたびご紹介してきた。この『新バランス理論』が次期極鋭ヒラメEXに盛り込めば究極の手感度に加えて今までにない理想の調子を実現できる確信があった。エサのイワシを違和感なく狙ったイメージ通りに泳がせ、いざアタリがあってからはより積極的に食い込みを促してくれる調子。ヤリトリにおいてもヒラメを釣り人のイメージ通りコントロールできるロッドが実現できる。そう期待を込めて次期モデルの開発の機会を密かに楽しみにしていた。
2モデルの極鋭ヒラメEXのうち、私がメインウェポンとしているのは決まって手持ち仕様のショートタイプ。ショートレングスの中にヒラメロッドに求められるすべての要素を盛り込むことはハードルが高いものだが、今回の極鋭ヒラメEX ⅯH-243は見事に私の期待に応えてくれた。ノーマルのヒラメ専用ロッドとしては史上最軽量の113gは圧倒的な手感度と操作性を約束してくれる。その一方で、オモリを背負ってホルダーに掛けた姿はあくまでもしなやか。ウネリによるオモリのハネを抑え、エサのイワシの動きに不自然さを与えない。だが、ひとたび手に取ると穂先の先端まで神経が通ったようなダイレクト感に驚かされる。この不思議な二面性こそ『新バランス理論』の真骨頂と言えるだろう。またアタリからアワセに持ち込む一連の過程も実にスムーズでスマートに仕事をしてくれる。ゆえにアワセのタイミングも実に把握しやすい。さらに、いざヒラメが掛った時も積極的にプレッシャーを掛け続けることが出来るだけでなく、水中のイメージがしやすいため自信をもってヤリトリが出来る。スムーズでパワーロスの無い曲がりはV-JOINT αの恩恵もあるだろう。
その一方で実釣を意識したこだわりとしてリールシートが挙げられる。柔らかくロッドを握ってアタリを待つ時間が長いとは言え、いざラインが船下に切り込む流しで大型のヒラメを掛けた場合や、良型の青物も相手にすることが有るヒラメロッドでは力を込めた握りをする場合も考慮しなければならない。前作に引き続き採用されたエアセンサーシートスリムフィットは実釣の場面場面に合わせた握りの自由度の高さは抜群だ。
実際に今回の極鋭ヒラメEXを手に取ってニヤッとしてしまう釣り人の多いかもしれない。私もその一人だ。さりげなくだがダブルアルマイト仕様のナット部分に浮かぶEXの文字。加えて立体的に輝くネームがフラッグシップであることを主張している。さらにロッド全体に偏光色が施されロッドの動きが生まれた際の印象をより鮮やかにしてくれる。曲がりの美しさや性能の高さに演出を加えてくれるDAIWAらしいデザインと言えるだろう。今回の極鋭ヒラメEXはヒラメ釣りの楽しさと共により思い入れも増してくれる見逃せないロッドとなっている。
この後、数年を経て私の注目する新しいDAIWAテクノロジーが生まれた。その名も『新バランス理論』。しなやかさと操作性という、一見相反する要素を高次元で両立する新しい設計思想だ。この『新バランス理論』であるが、船ロッドを一新させる可能性があることを私はたびたびご紹介してきた。この『新バランス理論』が次期極鋭ヒラメEXに盛り込めば究極の手感度に加えて今までにない理想の調子を実現できる確信があった。エサのイワシを違和感なく狙ったイメージ通りに泳がせ、いざアタリがあってからはより積極的に食い込みを促してくれる調子。ヤリトリにおいてもヒラメを釣り人のイメージ通りコントロールできるロッドが実現できる。そう期待を込めて次期モデルの開発の機会を密かに楽しみにしていた。
2モデルの極鋭ヒラメEXのうち、私がメインウェポンとしているのは決まって手持ち仕様のショートタイプ。ショートレングスの中にヒラメロッドに求められるすべての要素を盛り込むことはハードルが高いものだが、今回の極鋭ヒラメEX ⅯH-243は見事に私の期待に応えてくれた。ノーマルのヒラメ専用ロッドとしては史上最軽量の113gは圧倒的な手感度と操作性を約束してくれる。その一方で、オモリを背負ってホルダーに掛けた姿はあくまでもしなやか。ウネリによるオモリのハネを抑え、エサのイワシの動きに不自然さを与えない。だが、ひとたび手に取ると穂先の先端まで神経が通ったようなダイレクト感に驚かされる。この不思議な二面性こそ『新バランス理論』の真骨頂と言えるだろう。またアタリからアワセに持ち込む一連の過程も実にスムーズでスマートに仕事をしてくれる。ゆえにアワセのタイミングも実に把握しやすい。さらに、いざヒラメが掛った時も積極的にプレッシャーを掛け続けることが出来るだけでなく、水中のイメージがしやすいため自信をもってヤリトリが出来る。スムーズでパワーロスの無い曲がりはV-JOINT αの恩恵もあるだろう。
その一方で実釣を意識したこだわりとしてリールシートが挙げられる。柔らかくロッドを握ってアタリを待つ時間が長いとは言え、いざラインが船下に切り込む流しで大型のヒラメを掛けた場合や、良型の青物も相手にすることが有るヒラメロッドでは力を込めた握りをする場合も考慮しなければならない。前作に引き続き採用されたエアセンサーシートスリムフィットは実釣の場面場面に合わせた握りの自由度の高さは抜群だ。
実際に今回の極鋭ヒラメEXを手に取ってニヤッとしてしまう釣り人の多いかもしれない。私もその一人だ。さりげなくだがダブルアルマイト仕様のナット部分に浮かぶEXの文字。加えて立体的に輝くネームがフラッグシップであることを主張している。さらにロッド全体に偏光色が施されロッドの動きが生まれた際の印象をより鮮やかにしてくれる。曲がりの美しさや性能の高さに演出を加えてくれるDAIWAらしいデザインと言えるだろう。今回の極鋭ヒラメEXはヒラメ釣りの楽しさと共により思い入れも増してくれる見逃せないロッドとなっている。

SS/ⅯH-245
私自身、地元の外房、茨城方面でヒラメ釣りを楽しもうと思った時、ライトタックルを持ち出すことが多い。実際に軽いオモリが使用できるのであればライトタックルの方が至極快適で釣り人に伝わる情報量も多い。また、相手が大型のヒラメであってもライトタックルで十分対峙できると思っている。だが、ここ数年東北をはじめ地方へ足を延ばしたおり、ヒラメの型、数ともに圧倒的な魚影の濃さを目の当たりにした。さらに浅場で大ヒラメを相手にする状況を突き付けられ、いささかその認識に変化が現れた。この認識の変化が今回の極鋭ヒラメEX SS/ⅯH-245を生むきっかけとなった。
東北のヒラメ釣りでは、エンジン流しかつ浅場を攻めるイメージが強い。使用錘は80号のエリアもあるが、50ないし60号と軽めの錘で楽しめる海域も多いように見受けられる。ならばライトタックルを使いたくなるアングラーも多いはず。手持ちでタナを探る場合でも、軽く操作性の高いライトタックルは利点が多い。さらにそのしなやかな穂先は、高ダナの大型ヒラメ特有のモタレの表現力も高い。アタリを出すまではライトタックルの方が利点が多いと言えるだろう。
一方、大型ヒラメとのヤリトリに目を向けてみる。なんと言っても第一関門はフッキング直後のヒラメの動きを制すること。大型になればなるほど底から引きはがす時の抵抗は激しく、ヒラメがどう抵抗するかの予測が難しい場合が多い。いわゆる「底から離れることを嫌う」と言うやつだ。エンジン流しの場合、横流し(ドテラ流し)に比べ釣り人自らがしっかりとテンションを掛けていく必要があるので、なおさら大ヒラメをコントロールする難易度は高くなる。さらに浅場であれば近い間合いで、この「底離れを嫌う」抵抗を制しなければならない。この時ばかりはバットパワー、操作性ともにノーマルタックルが頼りになることも事実。パワーに余裕があればヤリトリにも余裕が生まれ、ヒラメの機先を制した暴れさせないヤリトリが出来ると言うものだ。
また浅場でのヤリトリでは、ヒラメが十分弱る前に取り込みをする事となる。いざタモ取りと言う時にこそ、釣り人がヒラメをコントロールすることが肝要となる。この時もノーマルヒラメタックルのバットパワーと長めのレングスが有利に働くことも多い。
東北のヒラメ釣りでは、エンジン流しかつ浅場を攻めるイメージが強い。使用錘は80号のエリアもあるが、50ないし60号と軽めの錘で楽しめる海域も多いように見受けられる。ならばライトタックルを使いたくなるアングラーも多いはず。手持ちでタナを探る場合でも、軽く操作性の高いライトタックルは利点が多い。さらにそのしなやかな穂先は、高ダナの大型ヒラメ特有のモタレの表現力も高い。アタリを出すまではライトタックルの方が利点が多いと言えるだろう。
一方、大型ヒラメとのヤリトリに目を向けてみる。なんと言っても第一関門はフッキング直後のヒラメの動きを制すること。大型になればなるほど底から引きはがす時の抵抗は激しく、ヒラメがどう抵抗するかの予測が難しい場合が多い。いわゆる「底から離れることを嫌う」と言うやつだ。エンジン流しの場合、横流し(ドテラ流し)に比べ釣り人自らがしっかりとテンションを掛けていく必要があるので、なおさら大ヒラメをコントロールする難易度は高くなる。さらに浅場であれば近い間合いで、この「底離れを嫌う」抵抗を制しなければならない。この時ばかりはバットパワー、操作性ともにノーマルタックルが頼りになることも事実。パワーに余裕があればヤリトリにも余裕が生まれ、ヒラメの機先を制した暴れさせないヤリトリが出来ると言うものだ。
また浅場でのヤリトリでは、ヒラメが十分弱る前に取り込みをする事となる。いざタモ取りと言う時にこそ、釣り人がヒラメをコントロールすることが肝要となる。この時もノーマルヒラメタックルのバットパワーと長めのレングスが有利に働くことも多い。

前置きが長くなったが、このことを踏まえた上で今回の極鋭ヒラメEX SS/MH-245の詳細をご紹介しよう。その全く新しい調子は穂先から穂持ちはライトヒラメ、バット部分はノーマルヒラメと言うもの。アタリを出すまでは前述のライトタックルの良さを、大型ヒラメがヒットすればノーマルヒラメタックルのパワフルなバット部分がより釣り人に有利なヤリトリを約束してくれる。ネーミング的にはSSが加わっただけであるが、実際に使用した感覚は全く違うカテゴリーのロッドと言っても過言ではない。もちろん極鋭ヒラメEXたる目の覚める様な軽さと感度、操作性はそのまま継承されている。すべてにおいて高次元なロッドゆえに、新しい感覚が非常に鮮やかな印象を与えてくれる。
軽い50号60号の錘であれば錘が底をトレースするような釣りも快適そのもの。その一方で、より大型のヒラメを意識して高いタナを探る場面でこの穂先は一段と冴えを見せてくれる。重めの80号の錘を使用した場合も高いタナで目感度を生かした釣りが面白い。しなやかになった分、目感の情報量が増えモタレのアタリの表現力が増しているからだ。高いタナでの大型のヒラメはモタレからアタリがスタートする場合が多い。こんな時もSMTならではのしなやかさと手感度は相変わらずの魅力を感じる。ヒラメロッドの理想を追求するうえで、SMTは未だに最高のDAIWAテクノロジーであると今回も再認識させられた思いだ。
また、ノーマルヒラメロッド最軽量となる109gの軽さも極鋭ヒラメEX SS/MH-245の大きな魅力だ。本来、目感度の範疇であるはずのモタレのアタリも、負荷の変化によって手でシグナルを感じることが出来るだろう。目感度と手感度で感じるモタレのアタリは、アワセをいれるタイミングを測る上でも釣り人にフッキングへと持ち込むためのビジョンを与えてくれる。
さらに地方によってはヒラメの釣りのエサを始めとした事情もさまざま。東北や常磐と一言で言っても冷凍のイワシを使う場合もあれば、活きたマアジを使うエリアも多い。また、瀬戸内海では大型のコノシロが特エサのエリアもある。いずれもヒラメの喰いこみと言う点では活きイワシよりも気を使うエサばかり。このような場合でも極鋭ヒラメEX SS/MH-245のしなやかな穂先は打って付けであろう。上記のエリアはいずれも大型のヒラメが高確率で期待できる海域だ。また、大型ヒラメばかりでなく青物や良型の根魚も意識した伊勢湾や関門海峡などのエリアであっても安心して使えるロッドとなっている。
そしていざ、ヤリトリとなった時は今までの極鋭ヒラメEXの強靭なバットパワーはそのまま受け継がれているため余裕のヤリトリが楽しめる。ここがこのロッドの真骨頂と言えるシーンだろう。全く新しい調子、その美しい曲がりと共に楽しむヤリトリは至福の瞬間だ。この際もSVFナノプラスのブランクスが手に伝えてくる情報は、理想のヤリトリをする上での重要な指針となる。その刹那の瞬間の情報に無意識にかつ適切に体が対応する。そんなヤリトリを目指していきたいものだ。釣り人次第で大型ヒラメとのヤリトリはまったく違う展開となる。大型のヒラメとのヤリトリは、ヒラメの出方を釣り人が感じ取り、機先を制してヤリトリ全体を釣り人が構築する。それが理想の大型ヒラメとのヤリトリだ。
軽い50号60号の錘であれば錘が底をトレースするような釣りも快適そのもの。その一方で、より大型のヒラメを意識して高いタナを探る場面でこの穂先は一段と冴えを見せてくれる。重めの80号の錘を使用した場合も高いタナで目感度を生かした釣りが面白い。しなやかになった分、目感の情報量が増えモタレのアタリの表現力が増しているからだ。高いタナでの大型のヒラメはモタレからアタリがスタートする場合が多い。こんな時もSMTならではのしなやかさと手感度は相変わらずの魅力を感じる。ヒラメロッドの理想を追求するうえで、SMTは未だに最高のDAIWAテクノロジーであると今回も再認識させられた思いだ。
また、ノーマルヒラメロッド最軽量となる109gの軽さも極鋭ヒラメEX SS/MH-245の大きな魅力だ。本来、目感度の範疇であるはずのモタレのアタリも、負荷の変化によって手でシグナルを感じることが出来るだろう。目感度と手感度で感じるモタレのアタリは、アワセをいれるタイミングを測る上でも釣り人にフッキングへと持ち込むためのビジョンを与えてくれる。
さらに地方によってはヒラメの釣りのエサを始めとした事情もさまざま。東北や常磐と一言で言っても冷凍のイワシを使う場合もあれば、活きたマアジを使うエリアも多い。また、瀬戸内海では大型のコノシロが特エサのエリアもある。いずれもヒラメの喰いこみと言う点では活きイワシよりも気を使うエサばかり。このような場合でも極鋭ヒラメEX SS/MH-245のしなやかな穂先は打って付けであろう。上記のエリアはいずれも大型のヒラメが高確率で期待できる海域だ。また、大型ヒラメばかりでなく青物や良型の根魚も意識した伊勢湾や関門海峡などのエリアであっても安心して使えるロッドとなっている。
そしていざ、ヤリトリとなった時は今までの極鋭ヒラメEXの強靭なバットパワーはそのまま受け継がれているため余裕のヤリトリが楽しめる。ここがこのロッドの真骨頂と言えるシーンだろう。全く新しい調子、その美しい曲がりと共に楽しむヤリトリは至福の瞬間だ。この際もSVFナノプラスのブランクスが手に伝えてくる情報は、理想のヤリトリをする上での重要な指針となる。その刹那の瞬間の情報に無意識にかつ適切に体が対応する。そんなヤリトリを目指していきたいものだ。釣り人次第で大型ヒラメとのヤリトリはまったく違う展開となる。大型のヒラメとのヤリトリは、ヒラメの出方を釣り人が感じ取り、機先を制してヤリトリ全体を釣り人が構築する。それが理想の大型ヒラメとのヤリトリだ。

「せっかく軽いオモリが使えるならそれに合わせた穂先を」とスタートした極鋭ヒラメEX SS/MH-245であるが、ロッドが形になるにつれ私の意識はより大型のヒラメを狙い撃つ方向ばかりに向いてしまった。また、まったく新しい調子ゆえ設計のシュミレーション段階と実際に使用した感覚が異なり、そのすり合わせにかなり苦労させられたロッドでもある。だが、実釣を重ねてしっかりと納得いく一本とすることが出来た。また、この新しい調子をいきなりスペシャルモデルたる極鋭EXで形にする大胆さが今のDAIWA船ロッドチームの勢いを感じる。一切の妥協なく最高のマテリアルとDAIWAテクノロジーをともに奢ったゆえ、新しい調子であるにも関わらずこの完成度を誇るロッドになったことは想像に難しくない。さらに使えば使い込むほど、新たなヒラメ釣りの楽しみ方を指し示す可能性に満ちたロッドであると私は思う。

北本茂照テスター MH243・S/MH272
ヒラメロッドの最高峰、極鋭ヒラメEXが新たなヒラメ釣りを約束してくれる1本に仕上がった。DAIWAテクノロジー『新バランス理論』により、ヒラメ釣りに必要不可欠となる、しなやかに食い込ませる調子と操作性のバランスという相反する2つの要素を高次元で両立。思い通りの操作が可能で、1日釣りをしても非常に快適だ。さらにバットパワーも向上しているので、大判ヒラメとこれまで以上に安心感を持ったファイトが可能となった。
ヒラメ釣りは1日のうちでも水深数メートルから100メートル近い深場まで攻めることもあり、流し方もエンジン流し、風を横に受けながらの横流しと様々。使用するオモリも状況で使い分けることも多い。だからこそヒラメ専用竿はどんな状況でもオールマイティーに対応できる順応力が必要となってくる。
生きイワシの動きを伝達する感度は何よりも重要で、本作ではテクノロジーの向上によってさらに高密度の情報を伝えてくれる。それによって、待つべきか、即アワセかなどのアワセのタイミングを釣り手が容易に判断できるようになった。では、実際どんな竿なのか。MH243はSMT(スーパーメタルトップ)をショート化することで感度と操作性が向上し、底ダチも取りやすくなっている。手持ちで激しい根周りの大型狙いなどでその性能を発揮する。さらに特筆すべきは、ノーマルのヒラメ竿としては驚異の113gを実現。「軽さは感度」は進化を続けている。
S/MH272は今までにない穂先のしなやかさを追求し、ヒラメに違和感を与えずオートマチックに食わせる調子に仕上がった。特に風を受けながらの横流し釣りにおいては想像以上の食い込みを実現。もちろんエンジン流しでもその食い込みの良さは変わらず針の掛かり方にも納得。長さはあるもののMH243同様に操作性も良く底ダチも取りやすく、生きイワシからの情報量も多く、アワセのタイミングが格段に向上したように思えた。
ブランクスはSVFナノプラスを採用。さらにねじれに強いX-45で補強。ジョイント部はV-JOINTαを搭載。1ピースロッド並みにしなやかに曲がり込みパワーロスを軽減しているので、大判ヒラメや不意の青物にも主導権を渡さずファイトが可能である。リールシートは力を込めたパーミングが可能なエアセンサースリムフィットを採用している。
さて、どちらのロッドを選べば良いのと思われる方も多いであろう。フィールドも違えば季節など条件も変わってくる。もし、「よりオールラウンドな1本を」と考えるなら僕はS/MH272をおすすめする。しかし、である。そこは、好みもや自身のスタイルなどを加味して選んで頂きたい。どちらにせよ、想像以上に期待に応えてくれる竿なのは間違いない。
ヒラメ釣りは1日のうちでも水深数メートルから100メートル近い深場まで攻めることもあり、流し方もエンジン流し、風を横に受けながらの横流しと様々。使用するオモリも状況で使い分けることも多い。だからこそヒラメ専用竿はどんな状況でもオールマイティーに対応できる順応力が必要となってくる。
生きイワシの動きを伝達する感度は何よりも重要で、本作ではテクノロジーの向上によってさらに高密度の情報を伝えてくれる。それによって、待つべきか、即アワセかなどのアワセのタイミングを釣り手が容易に判断できるようになった。では、実際どんな竿なのか。MH243はSMT(スーパーメタルトップ)をショート化することで感度と操作性が向上し、底ダチも取りやすくなっている。手持ちで激しい根周りの大型狙いなどでその性能を発揮する。さらに特筆すべきは、ノーマルのヒラメ竿としては驚異の113gを実現。「軽さは感度」は進化を続けている。
S/MH272は今までにない穂先のしなやかさを追求し、ヒラメに違和感を与えずオートマチックに食わせる調子に仕上がった。特に風を受けながらの横流し釣りにおいては想像以上の食い込みを実現。もちろんエンジン流しでもその食い込みの良さは変わらず針の掛かり方にも納得。長さはあるもののMH243同様に操作性も良く底ダチも取りやすく、生きイワシからの情報量も多く、アワセのタイミングが格段に向上したように思えた。
ブランクスはSVFナノプラスを採用。さらにねじれに強いX-45で補強。ジョイント部はV-JOINTαを搭載。1ピースロッド並みにしなやかに曲がり込みパワーロスを軽減しているので、大判ヒラメや不意の青物にも主導権を渡さずファイトが可能である。リールシートは力を込めたパーミングが可能なエアセンサースリムフィットを採用している。
さて、どちらのロッドを選べば良いのと思われる方も多いであろう。フィールドも違えば季節など条件も変わってくる。もし、「よりオールラウンドな1本を」と考えるなら僕はS/MH272をおすすめする。しかし、である。そこは、好みもや自身のスタイルなどを加味して選んで頂きたい。どちらにせよ、想像以上に期待に応えてくれる竿なのは間違いない。
発売月
2025.09=SS/MH-245
製品スペック
| アイテム | 全長(m) | 継数 | 仕舞寸法(cm) | 標準自重(g) | 先径/元径(mm) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 適合クランプサイズ | メーカー希望本体価格(円) | JAN | * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 極鋭ヒラメ EX MH-243 | 2.43 | 2 | 126 | 113 | 0.8/10.2 | 30~120 | 98 | SSS | 89,500 | 4550133337833 | * |
| 極鋭ヒラメ EX S/MH-272 | 2.72 | 2 | 141 | 118 | 0.8/10.2 | 30~120 | 98 | SSS | 91,500 | 4550133337840 | * |
| 極鋭ヒラメ EX SS/MH-245 | 2.45 | 2 | 127 | 109 | 0.8/10.2 | 20~100 | 99 | SSS | 89,000 | 4550133545931 | * |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※メタルトップご使用上の注意
■メタルトップの温度変化について
超弾性チタン合金は素材の特性上、5℃以下の低温環境では弾性が低下し、穂先の戻りが遅くなってくるという事象が起こります。早朝・夜間の極端な冷え込みや風の影響で、気が付く程度の曲がりが生じることがあります。更に0℃以下の環境で弾性低下は、より進行し穂先が曲がったまま戻らない現象が起こります。いずれの場合も気温が上昇すれば本来の超弾性に戻り通常のご使用が可能になります。
■過度な屈曲を生じるようなご使用はお避けください
メタルトップは、通常操作においては快適にご使用いただけますが、巻き込み・穂先の糸がらみ等外的要因による過度な屈曲には、クセ(塑性変形)が残ったり、また金属疲労により破損する可能性があります。
■万一のクセは、手で修正できます
万一クセが残った場合は、曲っている側と逆の方向にゆっくり曲げることで、修正ができます。ただし、クセの修正を繰り返しますと金属疲労の原因となりますので、巻き込み等クセが残るような操作はお避けください。
快適にご使用いただくため、取扱説明書は必ずお読み下さい。
■メタルトップの温度変化について
超弾性チタン合金は素材の特性上、5℃以下の低温環境では弾性が低下し、穂先の戻りが遅くなってくるという事象が起こります。早朝・夜間の極端な冷え込みや風の影響で、気が付く程度の曲がりが生じることがあります。更に0℃以下の環境で弾性低下は、より進行し穂先が曲がったまま戻らない現象が起こります。いずれの場合も気温が上昇すれば本来の超弾性に戻り通常のご使用が可能になります。
■過度な屈曲を生じるようなご使用はお避けください
メタルトップは、通常操作においては快適にご使用いただけますが、巻き込み・穂先の糸がらみ等外的要因による過度な屈曲には、クセ(塑性変形)が残ったり、また金属疲労により破損する可能性があります。
■万一のクセは、手で修正できます
万一クセが残った場合は、曲っている側と逆の方向にゆっくり曲げることで、修正ができます。ただし、クセの修正を繰り返しますと金属疲労の原因となりますので、巻き込み等クセが残るような操作はお避けください。
快適にご使用いただくため、取扱説明書は必ずお読み下さい。


