山間に位置する、人口740人の山梨県小菅村。自然豊かなこの村を流れる小菅川は、首都圏の水がめ・多摩川の源流域でもある。
「シモノシ(川の下流に住んでいる人々)に迷惑はかけられない」
この村の人々はそんな思いを胸にきれいな水を守り、そして川を守るために森を守ってきた。
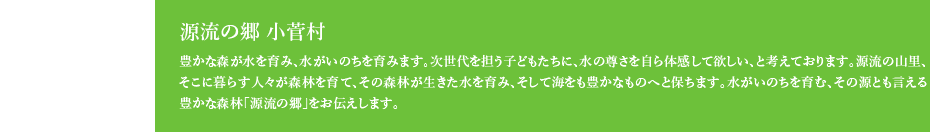
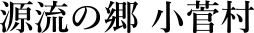



山間に位置する、人口740人の山梨県小菅村。自然豊かなこの村を流れる小菅川は、首都圏の水がめ・多摩川の源流域でもある。
「シモノシ(川の下流に住んでいる人々)に迷惑はかけられない」
この村の人々はそんな思いを胸にきれいな水を守り、そして川を守るために森を守ってきた。
人が多い都会に住んでいると、「人がいない、人の手が入らない自然こそがもっともいい自然なのだろう」と思いがちだ。しかし、第二回の探検で水源を守る森を訪れた時に、それが勘違いであることに気がついた。
人の手が入ることで守られる森林があり、しっかりと水を蓄える機能を持った森林や山が洪水を防ぐ。また、しっかり手入れされて山に蓄えられた栄養は、川を通って海に注ぎ、それが豊かな海を作る。人にとって自然が大切なように、山や川を守る人間は、自然にとっても大切な存在なのだ。小菅村は、自然と人が昔も今も相思相愛で暮らす地域のように思う。
そこで今回のBE EARTH-FRIENDLY源流探検部の探検は、「人と自然が相思相愛な小菅村の暮らし」を探ることにした。

今回の探検のガイド役を引き受けてくださったのは、小菅村役場 源流振興課の柳沢久智さん。この地に惚れ込み、移住したという人物だ。

「小菅村では、毎年5月4日に源流祭りが行われるんですよ。このお祭りは、多摩川の源流域である小菅村を、もっと多くの人に知ってもらおうと始まったもの。各地区ごとに村特産の味を手作りして、来場者をおもてなしするんです」
たった一日の祭りで来場者は1万人にも上るため、人口740人の村では文字通り村人総出でもてなすのだ。中でも人気なのが、地元の養魚場で育てたヤマメの塩焼きと、昔から各家で打って食べていた蕎麦だという。
「この地域では昔から蕎麦の実が栽培されていて、蕎麦の実を引く水車もあったんですよ。昔に比べて蕎麦打ち名人が減っているようですが、小菅村は水もいいですし、村の人にとって蕎麦は身近な食べ物なんです」。

蕎麦の他にも、村人にとって大切な農作物があるという。こんにゃくだ。山間にある小菅村は平地が少なく、田んぼを作って稲を育てるのには適していない。しかし、こんにゃくなら急斜面でも作れるうえ、高度成長期に換金作物としての価値が高騰。多くの家が栽培を手がけるようになり、こんにゃくは小菅村の経済を力強く支えたという。
柳沢さんは、現在も生産から加工・販売まで手がけるこんにゃく農家の日喜屋さんのところに私たちを連れていってくれた。

探検部を待っていてくれたのは、日喜屋の木下新造さんだ。日喜屋とは、木下さんの家で使われてきた屋号とのこと。木下さんが言う。
「山梨県では昭和の初め頃から県内各地で栽培を進めたのですが、その中で残ったのが小菅村でした。こんにゃくは平安時代に日本に入って来たそうですが、他の地域で品種改良が進む中、小菅村のこんにゃくは日本に入って来た当時の品種のまま残っていると言われているんですよ」
さっそく、こんにゃく畑を見せてもらうことにした。木下さんの後に続いてイノシシよけの扉をくぐる。すると、柳沢さんが「気をつけてくださいね」と探検隊を気遣ってくれるほど、急な斜面が目の前に現れた。

「この辺りでは麦とこんにゃくの2毛作をしていたんだ。今はこんにゃく畑に肥料用の麦を植えて、5月に刈り取る。すると、その後にこんにゃくの芽が出てくるんだ。今、畑から伸びてる青い草は刈り残した麦だね。麦は土の深いところまで根をはるから、集中豪雨が来てもこんにゃくが流れていかないんだよ」
畑の表面には乾燥したカヤや麦が斜面と平行にびっしりと敷き詰められている。木下さんがカヤをめくると、その下には木の葉が敷いてあった。
「こうすると土が活性化するし、夏に晴れ続きでも麦が湿度を保ってくれるんだ。こんにゃくは湿度がないとダメだから」


今年70歳になるという木下さんは、畑沿いの急な階段をすいすい上っていく。その後ろをなんとかついていきながら、「急斜面で作業するのは大変ですよね」と尋ねると、「慣れだよ、慣れ」と笑った。
「うちの畑は山の斜面を細長く切り開いた畑でね。掛け軸みたいだから、かけじく畑っていうんだ。こんにゃくは重さ500gくらいになったら収穫するんだけど、そこまで育つには3年から4年かかる。こんにゃくは寒さに弱いから、普通はいったん畑から取り出して貯蔵するんだけど、ここは日当たりがいいから、土の中で貯蔵できる。途中で取り出さなくて済むから、こんにゃくを傷つける心配もない。そして何より、ここは土がいいからね。下の方にじゃがいもを植えてるけど、これも美味しいんだ」

畑から戻ると、木下さんと一緒に工房を切り盛りしている奥さん、木下町子さんが、刺身こんにゃくを用意して待っていてくれた。

それは、私たちが知っているこんにゃくとはまったく違っていた。白いお皿の上でキラキラと光っている薄紅色のこんにゃくは、ふんわりと柔らかいのだ。臭みもまったくなく、つるりと喉を通っていく食感がたまらない。
「うちは手で成形しているからね。だからふんわりしているんだと思うよ。こんにゃくの作り方は五通りあるけど、うちは芋を大鍋で茹でてミキサーにかけて凝固剤を混ぜ、成形してまた火を通すんだ。小さな穴が開いてるから、煮物にしても味が染み込むんだ。昔は正月の餅つきの後にこんにゃくをついて茹でたし、冠婚葬祭でも大根や人参と一緒に煮たこんにゃくを食べたもんだよ」

昔に比べ、小菅村のこんにゃく農家は減っている。しかし、栽培だけでなく、加工・販売まで手がけることで、生き残る道ができたと木下さんは言う。
「他の人が作ったこんにゃくもうちで買い取ってるんだ。小菅村のこんにゃく作りを守っていきたいからね」
帰りに、木下さんが珍しいものを見せてくれた。「見てごらん」と促されるまま壁の中を覗くと、コンクリートで囲まれた、四角い場所に水が貯まっている。
「湧き水だよ。昔はこの水を飲み水に使っていたんだ。子供の頃は、あばくれて(暴れ回って)帰ってくると、まずこの水を飲んだもんだよ。何軒も家があってもみんな暮らしていけたのは、この村にはいい湧き水があちこちにあったからなんだ」

上下水道が完備された今では使っていないそうだが、その形跡を残しているところに、この村の人の水や自然に対する思いが現れているような気がする。やはり、この村の人とこの村の自然は、相思相愛なのではないだろうか。いつもとはちょっと違う探検は、羨ましくなるような「人の営み」を教えてくれたのだった。
世界が羨む豊かな日本の水、このような村の人たちに守られてきたことを次世代の支える子どもたちに伝えていきたいものだ。