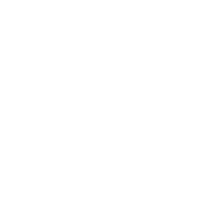巻く

歯のサイズを小さくすることなく、滑らかな回転を実現
次世代ベイトリールの根幹となる、新設計思想のギアシステムがハイパードライブデジギアです。
ベイトリールの駆動部において、その要となるのは、やはりギアでしょう。
ダイワリールのギアには、デジギアという名前を冠したギアが存在します。デジギアの素材は、アルミニウム、G1ジュラルミン、超々ジュラルミン、高強度真鍮などの金属で、釣種、用途に合わせ、適切なものを選択しています。
それらの金属をギアへと加工する工程において、デジギアは、ダイワ独自のデジタル解析によって割り出した、理想的な歯面(ギアの歯の形状)になるよう、歯面を精密な機械加工で整える、ひと手間を加えて仕上げています。これがデジギアの名前の由来です。
では、理想的な歯面、とは、一体、どんなものでしょうか? それはギアの歯の一つ一つが、対となるギアと、しっかり、がっちりと嚙み合いながら回転するもの。ダイワはそう考えています。噛み合いがよければ、力の伝達が良くなり、滑らかでスムーズな巻き心地が得られ、故障も少なくなるのです。デジギアは、歯面を精密加工で整えるという、そのひと工程を入れることで、高いレベルで噛み合い、強く、滑らかな回転をもたらしてくれるのです。
ハイパードライブデジギアは、工程こそ同様であるものの、まったく新しい設計思想に基づいて生まれました。ギアのモジュール(歯の大きさ)はそのままに、歯面がお互いに、よりしっかりと噛み合うような形状に進化させることで、さらなる滑らかな回転と、強さ(=耐久性)を実現しました。
専門的な話になりますが、ギア同士の噛み合いをよりよくするには、ギアの歯のサイズを小さくするのもひとつの方法です。すると、小さい歯が隙間なく噛み合い、滑らかな回転フィーリングが得られるのですが、反面、ひとつひとつの歯が小さいために、強度面では不安が残るのです。例えば、ハウジングや軸のわずかなたわみによって、噛み合いが少しずれたり、砂などの異物を噛み込んだりしただけでも、ギアが欠損する可能性は拭いきれません。そういう場面が積み重り、せっかくの初期性能が長続きしないというケースも起こりえるのです。
そこで、ハイパードライブデジギアでは、強度を確保するためにモジュールを小型化する手法を、あえて採用しませんでした。ギアの歯のサイズを一定以上、維持したまま、小モジュールと同等、もしくはそれ以上に滑らかな回転を目指す。その道を選んだのです。
滑らかな回転を生み出すには、それぞれの歯面による噛み合い率を高める必要があります。従来であれば、歯面の歯自体の数を増やすとともに、それぞれの歯の高さを伸ばす手法が用いられてきました。
それに対して、私たちダイワが目を向けたのは、歯面の「圧力角」です。圧力角というのは、シンプルに説明すると、歯面が立ち上がっている角度のことです。この圧力角を、ハイパードライブデジギアでは、緻密な計算のもと新たに設計し、バレット型のようなシルエットを導き出しました。
通常、ギア同士が噛み合うときに接触する箇所は、一般的な形状では2点です。それに対して、このバレット形状では最大3点で接触することを理想とすることで、滑らかな回転を実現したのです。また接触が分散されたことで、モジュールサイズも相まって滑らかな回転が長く続くことにつながりました。それだけなく、ノイズレベル(巻き上げ時のザラつきなど)も従来品と比べ、50%以下(当社比)まで低減したのです。この理想的な噛み合いを実現しているのが、駆動の要となるドライブギアとピニオンギアの噛み合い部分です。
ハイパードライブデジギアが、滑らかで静かな初期回転が長く続く理由には、こうした秘密があるのです。
HYPERDRIVE DIGIGEAR
スペシャルコンテンツ