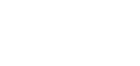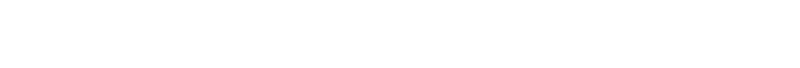リールに「軽さ」と「強さ」をもたらすモノコックボディ。18イグジスト、19セルテートを例にとると、モノコックボディ非搭載の前作に比べて、自重にして30g以上、大幅に軽量化され、強さの指標のひとつである巻き上げ効率は15%もの向上を果たした。
つまり、今までと同等番手の、モノコックボディ搭載リールを手にしたならば、まずは「軽さ」がもたらす恩恵を心から実感していただけるはずだ。
- キャスト時の振り抜きが速くなり、飛距離が向上
- 自在な操作が可能となり、さまざまなアングルからテクニカルなキャストが繰り出しやすくなるとともに、ルアーアクション時やファイト時のハンドリングも向上
- 感度が向上
- 疲労感が軽減され、集中力が長時間持続する
そして「強さ」がもたらすものは、
- 魚とのやり取りにおけるパワー
- 初期性能がより長く持続
だが、モノコックボディが秘めるポテンシャルには、もっと奥がある。今回は、それを少し読み解いてみたい。
例えば、軽さだ。強度がアップしているということは、ターゲットによっては、従来よりひとつ下の番手でも、強度的に十分に足りる場合がある。もちろんラインキャパシティや、快適に巻けるハンドル長さ、タックルバランスなどとの兼ね合いもあるので、一概にはいえないけれども、ある一定強度を満たせば大丈夫だというのなら、小さな番手を選ぶ選択肢も出てくるではないか。
番手が小さくなれば、当然、劇的に軽くなる。軽量化をとことん追求したいなら、そんな選択肢もある。頭の片隅に入れておいていただきたい。
また、逆も然り。今までのリールの重量に不満がないのであれば、あえて大きな番手を使って、さらなるパワーを得るという選択肢もある。つまり、リールを選ぶ際、「強さ」を基準にするなら軽さを得られるし、「重さ」を基準にするなら強さが得られる、というわけだ。
ひとつ例を挙げよう。19セルテートのLT5000D-XHは、耐久テスト時にドラグフルロック状態で、10㎏クラスのヒラマサを何本も獲りまくり、アフターチェックでも、不具合が出なかったほどの強度を誇る。なのに、自重は295gだ。これまでショアジギングや、オフショアのライトキャスティング、ライトジギングなど、従来は自重400gオーバー、ときには500gクラスのSWモデルのリールを装着しないと太刀打ちできなかった釣りが、今や300gアンダーのリールで楽々悠々とは驚く。
300gアンダーのリールといえば、従来では3000番クラス。ということは、シーバス用としてもストレスなく使えるうえ、もっとパワーの必要な釣りもまかなえてしまうということだ。もちろん、アングラーの技量やタックルバランスなどが介在してくるので、一概にはいえないが、ジャンルによっては、これまでの標準的なタックルセッティングを、一変させてしまうほどの可能性を、モノコックボディは秘めているのだ。
同じ強さなら軽く。同じ重さなら強く。

同じ重さなら強く
新旧イグジストの自重を比較すると、旧の2508PEと、新のLT3000-XHが、ちょうど同じ195g。ひと番手、大型のボディサイズに大きいドライブギアを内蔵して、パワフルになったものと同重量なのだ。2500番サイズは、港湾や河川内のシーバス、エギングなど、多用途に使えるが、3000番サイズは外洋サーフなどにも対応。大は小を兼ねる汎用性を備えつつ、同重量なのである。

同じ強さなら軽く
今回、ピックアップしたいのは、5000番クラス。ワラサやハマチクラスのブリ族、中型のヒラマサ、サワラ、シイラなど、従来は、SWモデルだと重く、汎用機の大型番手ではパワー不足だと悩んでいたところをすっぽりと埋めてくれる、ミッシングリンクのような存在が、がっしりとしたモノコックボディのセルテートの大型番手だ。タックルセッティング次第では、軽やかなビッグゲームが楽しめる。