|
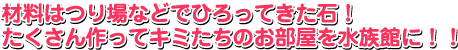
楽しく、大好きな魚にふれあえる!?
さかな釣りをテーマにした、大好評の手づくり教室。
材料は、川や浜辺にある石だ~。

この石で作るお魚アートは、さかなの形に似た石をひろってペイント(色つけ)する『さかなストーンアート』。
もちろん、作り方はとてもカンタン。
色つけなどのテクニックもわかりやすく説明しているので、とにかくチャレンジしてみてください!!
たくさん作ってお部屋にかざれば、オリジナル(自分だけの)水族館(?)だって作ることもできるはず・・・。
こんな楽しみ方ができるのも石で作るお魚アート(=スートンアート)教室の面白い点だから・・・ね。
作り方を教えてくれる先生は…
八百板浩司(やおいた こうじ)さん
《プロフィール》
さかな、つり、自然をテーマにした作品を手掛けるイラストレーター・八百板さんが、イラストにひき続いて今回も先生だよ。
八百板さんは、日本のみならず、アメリカのフィッシング誌などでもリアルなイラストを執筆し、
ワールドワイド(世界的)な活躍を続けている有名人。そんな先生が、上手に描くワザを教えてくれるからね。
|