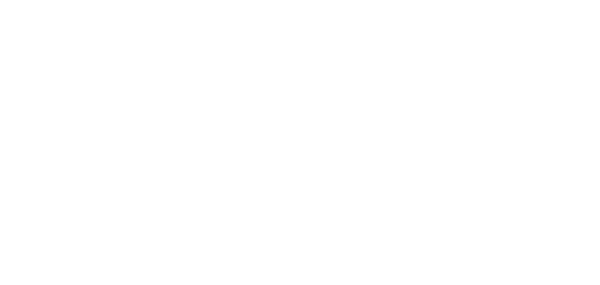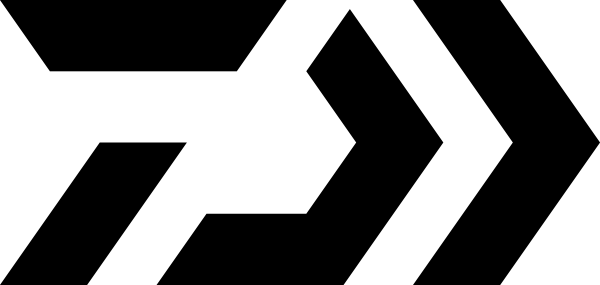-
川村 光大郎


時代の今を見つめ続ける
“真のバーサタイル”
陸の競技を極めし者が求めた6本。
ショアコンペティション、10年間の足跡。
「バーサタイルロッドという言葉はある時から存在していた。しかし、“真のバーサタイル”は存在していなかったのも事実だった」
Versatile。それは多用途や多彩、また万能の意味を持つ英単語。バスフィッシングの世界、それもロッド界では、いつしかそれが一人歩きするようになった。川村光大郎はそう語り始めた。
「あらゆるルアーが使えるのかもしれない。しかし、それは単に巻きも撃ちも含めた全ての釣りの真ん中を突いただけのものであって、どのルアーを使うにしても及第点に及ばない。それでは僕が大事にしている競技の世界では通用しない」
川村は今から18年前にスタートした陸王の初代王者にして、現在に至るまでに史上最多となる5度のタイトルホルダーに君臨。今なお陸の競技界で最前線を走り続けている。
そんな川村が手がけるバスロッドシリーズ『STEEZ Shore Conpetition』が産声をあげたのは今から10年前、2016年のことだ。
「あの頃求めていたのは1本で僕の釣りが何でもできる竿。当時の陸王は、竿1本ルールだった」
2日間の公式プラクティスを経て、戦略を絞り込む。撃ちか巻きか、それともフィネスか。タックルを入念に選抜しても、突然のフィールド変化に直面すればもう後戻りはできない。どんな状況に陥っても幅広いルアーが使える竿、釣り勝てる竿の開発は、川村にとって急務だった。
当時、川村にとって最大の戦力だったのがスナッグレスネコリグ。そしてここ一番でのスモラバ。時にスピナーベイト、時に中型ハードベイトまで登板する機会もあった。
「対戦で使うルアーの数々を考えると、ベイトフィネスという選択肢に行き着いた。それが自分にとって、真のバーサタイルとなる可能性があると」
川村光大郎×ベイトフィネス=真のバーサタイル。これがSTEEZショアコンペティションの始まりだった。
革命機SVに頼らない
本当の1本を求めて

2010年代前半、川村が最も多用していたロッドがブラックレーベルBL PF701MFB。本来は撃ち物を目的とした1本だが、使い込んでいくうちに可能性が広がっていった。
「当時の僕がバーサタイルと言えた唯一の竿。MediumパワーでF(ファスト)テーパーを意味するMFBだが、バットにはMHの強さがあった。カバーゲームはもちろん、投げた先でのフッキングも決まり、プラグさえも使えた」
この1本が川村の主軸となり得たのは、2013年に『STEEZ SV』という新たな武器が登場したためだ。初代STEEZに、替えのSVスプールへと換装すればより軽いルアーさえもスムーズに扱えたのだ。
「ただ竿は軽いとは言えなかった。STEEZだからこそ採用できるSVFコンパイルXを使えたら、どんな竿ができるのか非常に興味が湧いた」
真のバーサタイルロッドへと向けた明るい未来を予感させた。だが、意外にも開発は難航した。SVFコンパイルXの軽さと高感度、そして高反発を、それまで使い込んできたBLPFのテーパーに落とし込むと、求めていた理想から徐々に遠のいていったのだ。
「下まで曲がるテーパーにして、軽いものや巻き物にも使えるようにもしたい。一方で、その頃は撃ち物がよく釣れていた時代で、それまで以上に足下のカバーフィッシングがメインになった。テーパーを寝かせると、カバーでのフッキングパワーが落ちる。FテーパーかRテーパーか。その匙加減はどこなのか…」
理想にマッチする1本が仕上がらない。迫る納期。とはいえ、イメージと完全に重なるモデルを作り上げることは川村の使命。納得のいく1本を作り上げることに専念し続けた。
「今思えば、当時はロッド開発の知識が浅く、イメージがあってもエンジニアへの伝え方が未熟だった。SC各モデルの開発が進んでいくと、DAIWAの技術力も格段に上がっていく。同時にフィールドも刻々と変化し始めていった」
2016年、SC6111M/MHRB初代ファイアウルフが完成。足下のカバーにおけるマイクロピッチ局地戦が主力だった時代を象徴する1本だが、いつしか個体数の減少に伴い攻略範囲を広げることが主だった展開となっていく。
「次なるモデルの構想がまとまっていく。レングスは取り回し良い6ft.9in.へ。Rテーパーをより深くしてキャスト精度を向上。レンタルボートでも使いやすい。5年を経て新たな要望が出てきた。SCは必然性のあるモデルチェンジしかしない」
2022年、いよいよ2代目『ファイアウルフSC C69M+-ST』が産声を上げることになった。
「新素材前提の開発はない。
不用意にモデルチェンジしない」

「4年経った今でも全く不満がない。2代目ファイアウルフで僕の求めるものに完全にハマった。新たな要望はない。それは軽い悩みでもある」
22ファイアウルフは最も使用頻度の高いバーサタイルにしてラフに扱うことが多いにも関わらず、強度に何ら不安がない。優れた使用感と共に、今なお絶大なる信頼を置く1本だ。
「ただ、DAIWAの技術力は日々進化している。不用意なモデルチェンジはしたくない自分がいる一方で、新たに試せることは増えていく。1本1本の適性をみた上で、SCがより良くなる可能性を探ってみたい」
今季2026年に登場の『SCライトニング64 C64ML+-LM』がまさにその好例だ。
2021年に登場した初代SCライトニング66 C66ML-GはSVFグラスを用いたソフトティップを採用して、クランクやシャッドクランクなど、ハードベイトの中でも使用頻度高いルアーのために開発したモデル。だが、時代の変化はリニューアル構想へと川村の背中を押した。
「ただ巻き系が釣れにくく、出番が減りつつあった。バーサタイルを求めるSCでありながら出番が減ったルアーを重視するのは本末転倒。SCの1本という役割の中で最大限の汎用性を持つコンセプトから外れてしまっていた」
現代の戦力となり得るポッパーやジャークベイトへの対応力、ワイヤーベイトでのキャスタビリティやフッキングパワーをより重視。ただ巻き系への対応力も可能な限り扱える範疇に仕上げた。
「メイン素材は低弾性カーボン・LowModulus。細身肉厚のブランクに仕上げ、根元にはトレカ®M46Xを採用。低弾性LMで損なわれる張りを、高感度高反発の新素材で根元を補強できた」
6ft.4in.。初代から2in.のショート化へ。
「下方向へジャークしやすく、水面を叩かない。ただ巻き系にしても存分で操作性は格段に向上。両立できるバランスに仕上がった」
またカーボンガイドAGS、同じくカーボンスレッドCWSも採用へと至った。
「開発途中まで中弾性+チタンSICが第一候補だったが、最終的には低弾性+AGSへ。キャストフィールに難があった低弾性も、軽いガイド・AGSによって曲がっても戻りが早くなる。テイクバックからルアーを送り出してくれる感覚が向上した」
可能性は探り続ける。「もう少しこうしたい」の限界を見付ける旅。それがSCの開発姿勢だ。
可能性の追求、限界への挑戦
遠回りが導いた本当の1本

プロトサンプルを絞り込んでいく作業は5本から1本を選抜。そこからバージョン違いを5本、そして1本を選抜。この繰り返しが続く。
「竿作りに計算式があったとしても、実際に物を作らないと判断できない。求めた1本が仕上がったら、その周辺も探る。そうすることで1点を絞れる。バージョン違いが少し良くなることもあれば、悪くなることもある。そこで1点が見定まる」
通常プロトは、テクノロジーや情報の流出を防ぐため、テストが終われば回収されるものだ。しかし、川村はテスト1日では完全に判断できないことを訴えた。
「陸王でもテストサンプルを使ってきた。攻めて攻めて攻め上げてこそ見えてくることもある。そこを次にフィードバックできる」
2020秋、大江川・五三川で行われた陸王決勝では、川村の右腕には翌年に発売を予定する21ファイアフラッシュS64L-SV・STプロト。ライトキャロやダウンショットを駆使して川村は栄冠を獲得することに成功した。
「SCがこれまでに多くの方に支持されて、2巡目からより独立した立ち位置になれた。ブランクだけではなく、当初は難しいと言われた1本ごとのカラー分けも可能になった」
陸は無論、竿数を制限されるレンタルボートでの釣り。ひと目で持ち替えることができるのは大きなメリットになる。例えば、ボイルの瞬間はこの一瞬の差が明暗を分ける。
川村はSCの6本にそれぞれが可能な限りの幅、可能な限りの汎用性を込める。そのこだわりの開発姿勢は、ふたりめのショアコンペティター、佐々木勝也にも受け継がれたのは必然だった。