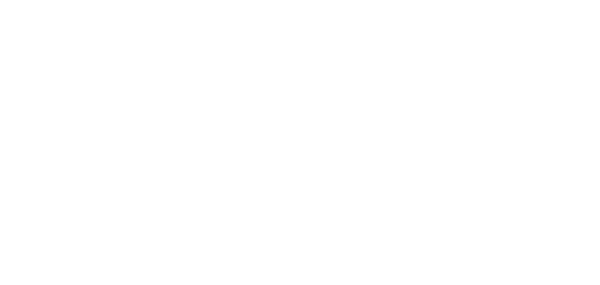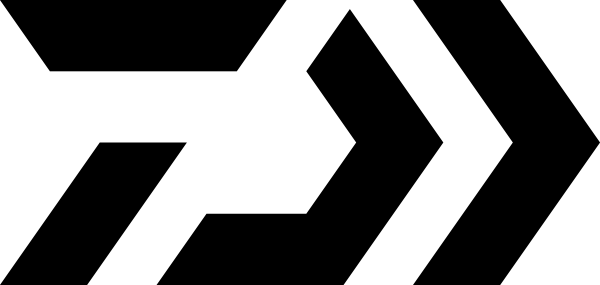-
並木 敏成


究極の現場、実釣能力の検証
「勝つために」始まったSTEEZ
Bass or Die…釣るか、さもなくば死か。
STEEZロッドの根底に流れる、揺ぎなき精神。
STEEZが世に衝撃を与えたのはリールだけではなかった。ロッドも同時にDAIWA最高峰バスフィッシングブランド・STEEZの名を冠しての登場となった。今となってはルアーも同ブランドを掲げるトータルブランドとして知られるが、当時としては非常にレアケースでおそらく世界的に見ても前例のない試みだった。
STEEZ発祥の2006年といえば、並木敏成は第2期の渡米で、FLWツアーに参戦中のこと。前年の2005年は全6戦中の4戦でトップ5を獲得、年間成績2位を獲得した「T.NAMIKIのグレートイヤー」。その第3戦ワチタリバーでは見事に優勝。使用したプロトロッドは、翌年にワチタのサブネームを冠してリリースされたことは記憶に新しいところだ。
「ハリアーの1ランク上のパワーを持つモデルで、メインパターンは、当時としてはまだ稀有だったPEラインを組んだレイダウンでのフリッピング。キャスタビリティの高さはもちろん、アクションが付けやすく、何よりパワー負けしない1本だった」
そう、その頃は翌年のSTEEZバスロッド発表のため、数々のプロトを実戦で使い込んでいた。
究極の現場、トーナメントにおける実釣能力の検証。それは、まさに並木の座右の銘を象徴していた。
『BASS or DIE』。意訳するなら『(バスを)釣るか、さもなくば死か』。
太平洋の向こう側、広大な大陸を転戦するサムライ。群雄割拠のFLWツアーで孤軍奮闘する並木の姿は、世のアングラーの心を打った。それはDAIWA開発陣も例に漏れず、TEAM DAIWAの意志を継ぐ、次なる最高峰ブランドの名を並木にこう打診したのだった。
『BOD(読み:ボッド)』。
それは並木の座右の銘の略称だ。だが、並木は首を縦に振ることはなかった。
「俺のブランド。そんなイメージが強過ぎた。ましてや日本とアメリカを往復する日々の中で、すべてをひとりでこなすのには無理があった。今で呼ぶところのDAIWA WORKSメンバーが皆で作り上げていくのが筋ではないかと」
米国9ヶ月、日本3ヶ月。毎日のように湖上に浮いて、プラクティスから試合へと。終われば次の開催地まで1日1,000kmを超える移動も辞さない米国ツアートレイル。一方、国内では息をつく暇もなくメディア活動に加え、新たなタックルのテスト及びミーティングの日々が延々と続いていた。
アクセシビリティを増す
代々継承のコードネーム

「今も昔も開発姿勢にそう変わりはない。飽くまでも世界基準のモノづくり。少なくとも自分の場合は作ったものがそのままアメリカで使える。もちろん日本でも存分に使えるものを目指したことは言うまでもない」
程なくして、DAIWAから次なるブランド名の候補として上がったのが『STEEZ』。米国ではSTYLEのスラングとして使われる言葉で、文字通りスタイル、流派や姿勢などの意味を秘める。
STEEZバスロッドの開発は、主にベイトモデルを並木が担当。初年度はラプター、トップガン、ブリッツ、フロッガー、ハリアー、ワチタ、ストラトフォートレスの7本。
一方のスピニングは川口直人が担当。ヘルファイア、スカイフラッシュ、ルガー、キングボルト、グレイゴーストの5本だ。
「元々は自分が開発時に、バトラー時代からのコードネームを引き継ぐ方がイメージしやすいので使っていた。結果として、現代まで続くことになった」
その多くがTDバトラーから引き継ぐ戦闘機をイメージしたコードネーム。その名の継承は、先代からのユーザーもロッドの用途を想像しやすい。
「その時代のベストを常に追求するDAIWA。その意味では、TDバトラーリミテッドは本当に衝撃だった。とにかく軽く、超感度。今なお感覚が忘れられないというアングラーも多い」
当時としては破格の高弾性・SVFコンパイルXをすべてのモデルに採用した。
「ただ撃ちと巻きのいずれにも採用するには無理があった。用途によって素材を使い分けるべきで、テクノロジーの適材適所化は必要だと」
並木は次世代ロッド・STEEZの開発条件を提案したのだった。
BATTLER LTDからの脱却
適材適所の素材と製法へ

「例えばブリッツ。クランクベイトを始めとしたプラッギングを完遂するには、先代の高弾性はマッチしない。どうしてもレギュラーテーパーに仕上げた低弾性のLM(LowModulus)が必要だった」
初期12機種はモデルそれぞれにテイストを合わせた。またSTEEZがユーザーに向けて画期的だったのは、採用されたマテリアルごとに異なるリールシートのカラーを採用したこと。シルバーはSVFグラファイト、レッドはSVFコンパイルX、ブラウンはLM、ブルーはUSトレイル。今なお、その差し色の伝統は続いている。
各部の詳細に目を向ければ、リールシートはエアビームコンストラクションを採用。中空の内部をブランクが貫通し、感度が向上。強度を存分に保った上で、薄肉ロープロ化。軽量化が間違いのない進化を遂げた。
またフォアグリップは極限まで肉をそぎ落としたショートフォア。「抜き上げ時はブランクスに手を当てればいい」という並木のアイデアが活かされた。さらにこの軽量感はシングルハンドでのキャストしやすさにも貢献したのは白眉だった。
また並木が手がけてきたモデルの中でも、最も広く知られているコードネームのひとつがハリアー。その初代から深堀りしていくとすればSTEEZの歴史が見えて来る。
時代と共に進化を遂げる
名竿・ハリアーの系譜

「元々は7ft.1in.のヘビーアクション。バトラー初年度にBA7011HFBを作り上げ、STEEZではその血筋を受けた06STEEZ7011HFB-SV、17年のリブランディングで7011H/MHFB-SVへ。21年の2代目STEEZではC610H-SVへと進化を遂げていった」
2000年当時はカバーをテキサスやジグでピッチンフリッピンだけで攻めに行く竿の究極を目指した。国内では個体数に陰りが見えてきた頃だが、時と場所を選べばカバー撃ちだけで存分に釣果が得られた時代だ。
「遠くに投げなくても足下だけでいい。高弾性のアドバンテージ、軽さを活かして、長さを持たせた超感度竿に仕上がった。06ハリアーで気持ちマイルド化した感がある。それはバックスライドなど高比重ノーシンカーの撃ちものが求められ始めた時代に応えた形」
一時はトーナメントレギュレーションの最長限ロッドとなる8ft.のハリアー80も登場。それまでと同様のカバー撃ちを求める際には、よりスペックアップしたモデルが担った。
「3代目の17モデルは、レンタルボートフィールドや陸っぱりでの使用も視野に入れて、6ft.10in.までショート化。それまではビッグベイトなど大型ルアーも守備範囲だったけど、15マシンガンキャスト3 691HMHFBが完成して、ハリアーは時代の流れを捉えたモデルに仕上げた」
そして今季26年、STEEZとしては4代目となる『ハリアーC71MH+-SV』が誕生する。
「26モデルはマテリアルが明らかに1ランク上のものが登場する。まさに素材革命と言っていい。自分が求める理想に、技術が追いついてきた」
時代の変化と共に、竿へと求める矛先は変わり続ける。バーサタイル性もそのひとつ。基本のテーパーバランスは変わらず、常にブラッシュアップを遂げていく並木の竿。根底にあるのは時代時代に合わせた、飽くまでも実釣主義だ。
「釣り味より釣果で示す、切れ味鋭い刀。状況に合わせて戦闘機でやっつける、隙を与えない200%の竿作り」
かつてのTDバトラーリミテッドやSTEEZレーシングデザインを彷彿とさせる圧倒的な超感度が26STEEZの真骨頂だ。
「これが最終局面。そんな覚悟で作り込んだ」
感度を底上げしたのはトレカ®M46X、高弾性を維持しつつ強度を約20%高めた新たなるカーボン繊維を採用。DAIWAはその繊維を極限までレジンを削減したプリプレグへと昇華して、SVFコンパイルXを始めとした最先端の製法で巻き上げた。何物も到達していない超感度の領域へと。
「千里眼? 随分と控えめだね。万里眼でもいいくらいだよ」
フィールドの隅々までを見通せるかのような透き通った超感度を味わえる26STEEZ。そのトータルコンセプトは千里眼。仕上がったモデルを軽快に操作、鮮やかに獲物を仕留めるや、並木のジョークが冴え渡った。