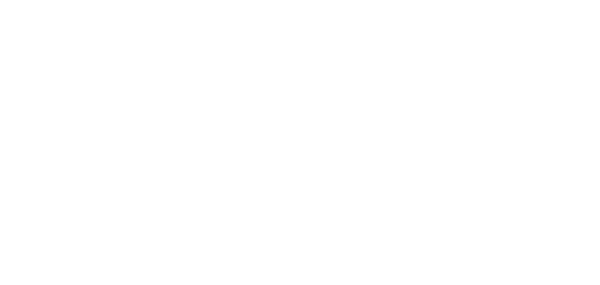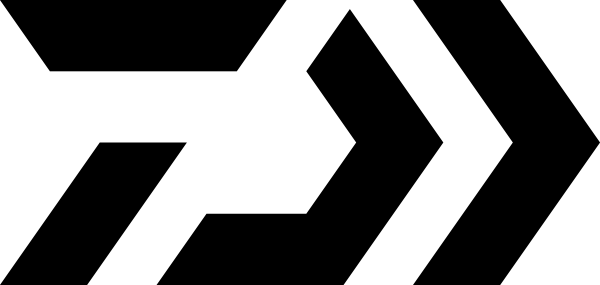-
川口 直人


マニュアルからオートマへ
STEEZ AIR誕生前夜、革命の始まり
第3世代STEEZへと繋いだ原石T3 AIR。
ベイトフィネス新時代が幕を開けた。
“ベイトフィネス”。それは現代バスフィッシングにおける主流のひとつ。その歴史は比較的浅く、日本が世界へと発信した数あるメソッドのひとつだ。
2000年代後半にK.T.F.沢村幸弘氏が提唱するや浸透し始め、2010年代には年を経るごとに熟成して一気に隆盛した感がある。いち早くその有効性に着目したトーナメントプロたちは、日々試行錯誤を続け正解への糸口を探っていったのだった。
5gを下回る軽量ルアーを如何に精度高くターゲットの居場所へと送り込めるか。初期はロッド、リール共に明確な指標は見付からない。かつて2000年代初頭にパワーフィネスがそうであったように、自作やチューニングなどが盛んに行われていた時期でもあった。
その頃、ベイトフィネス黎明期にいち早く注目されたベイトリールといえば、リベルトピクシー。小型かつ軽いルアーを快適に扱える軽量コンパクトを謳ったファンフィッシングの代名詞的存在だった。ところがアンテナが鋭く立ったトーナメントプロたちは、このモデルを如何に実戦投入すべきかに日夜明け暮れていたのだ。
しかし、元々小型の巻き物を守備範囲としていたリベルトピクシーには限界があった。現代では巻き物に使われるギア比5台は、撃ちにおいてはディスアドバンテージとなる。
霞ヶ浦を主舞台とする赤羽修弥や橋本卓哉、トップ50で全国フィールドを巡る川口直人らのハイギア化の強い要望。DAIWAがそこに応えたのが件のリベルトピクシーをベースとするPX68。その数字がギア比。先代の小型の筐体に仕込める最大のギアは6.8が限界だった。それでもフィールドの変化に敏感なアングラーは飛びついたものだ。
「まだまだベイトフィネスがどんなものなのか、ハッキリとわからない、何が正解なのかもわからない時代だった」
ベイトフィネスに傾倒し始めていた川口直人は、当時をこう振り返った。
「リールに失礼だ」
右から左へ巻きの矯正

「ベイトフィネスに真剣に取り組んだきっかけは2013年リリースのT3 AIR TW。軽いものでもφ32mmスプールがよく回る。さらには当時の最速ギア比8.6。開発テストでその存在を知って、コレってすげえことができるんじゃねぇかって」
開発にはあのベイトフィネスの父・沢村幸弘氏が参画した最初期作。その時受けた衝動は長らく心から消えることがなかった。
「何より3.5gが普通に投げれるリールなんてなかった。そこが衝撃。ベイトフィネスがさらに研ぎ澄まされてきたなって」
リリース前年の秋、春のリリースまでの半年間。川口は左巻きリールを完璧に使いこなすべく、自主練習を繰り返した。
「こんなすげえリールが出るなら、右巻きで竿を持ち替える手間がもったいない。左巻きでより効率の良い釣りに切り替えなきゃリールに失礼だって」
試合で使うなら100%では不十分。「120%で戦える」状態へと自身をストイックなまでに追い込んでいった。
手元に届いたT3 AIR TWは、その前年に仕上げたSTEEZハーミットに組み込まれた。SVFコンパイルXを採用したハーミットはブラックにオレンジの差し色。川口のベイトフィネスコンボはそれぞれ配色を示し合わせたかのようなマッチングを見せる。川口が善戦してきた試合の多くは、その実弾にネコスト(現STEEZネコストレート)を選抜。3種の神器とも言えるマネーベイト、いやマネータックルとも呼べる存在だった。
T3 AIR TWが後のSTEEZに多大なる影響を与えたことは言うまでもない。現行モデルへと続くTWS、G1ジュラルミンスプール、そしてエアブレーキシステム。STEEZの名を冠せずとも、ルーツを辿れば現行第3世代へと続く礎だったことは明らかだろう。
実用範囲の明確化
ベイトフィネスの熟成

その後、T3 AIR TWはSTEEZハーミットと共に長きに渡り、川口の主戦力のひとつとして第一線で活躍してきた。他のベイトフィネスリールが続々と登場したのもこの時期だが、それらには目も配ることもなかった。
「誰よりも長く使ったと思います。キャスト後半の伸びがどれよりも秀逸。キャストがバッチリ決まるのはこれしかなかった。だけど、足掛け8年ほど使い込んできた2020年。あれだけ好きで使い込んできたT3 AIR TWをいよいよ手放す時が来た」
それが『STEEZ AIR TW』だった。TWS・G1ジュラルミン・エアブレーキシステムはそれぞれ進化を果たして、オープンフラップ型からターンアラウンド型へ、φ32mmからφ28mmへ、など劇的な進化を遂げたのだ。
優れた回転性能はロッドを鋭く振らずとも狙いのスポットへ低弾道で飛んでいく。突き抜けるライン放出性能の一方で、エアブレーキは低速時と高速時で最も適したブレーキ力を生み出す。先代のベイトフィネス機との比較で最も進化を遂げていたのは、ブレーキ設定だった。
「一度ブレーキ設定すれば、再設定する必要がない。かつては3モード×20段階、合計60段階ある、いわばマニュアル車。性能は申し分ないけど、ユーザーを置き去りにしていた感もあったのは事実」
この頃にはベイトフィネスのメソッドも熟成を遂げ、実用的なリグ総重量は4〜5グラムと認識。その範疇にブレーキ力を一度決めれば、オーバーヘッドでもピッチングでもトラブルなく自在なキャストが可能となる。いわばプロアングラー目線のF1カーから、オートマ車へと変換したイメージだ。
「T3 AIR TWの頃はまだまだベイトフィネスが成熟していない時代だった。投げることができるルアーを1gでも軽くしたい。そんな方向性が強く、実用範囲をないがしろにしていたのかもしれない」
DAIWAベイトフィネスの進化はリールのみならず、無論ロッドにも注がれていったのは自然な流れだった。
AIR、ハーミット、ネコスト
=STEEZ“三種の神器”

「ネコストレート5.8インチのネコリグ、各種小型プラグ、トレーラー合わせて5g前後のスモラバ」
いつしか定着していった5gという、ベイトフィネスの数字。無論、時にそれより軽いものも使う場合もある。だが、実用的な範囲、スイートスポットはそこにあった。
「初代ハーミットを作った頃はベイトフィネス黎明期だったこともあって、基本的な考え方としてスピニングでは重い、ベイトでは軽いルアーを投げるための中間的な存在として開発がスタート。ベイトフィネスがどういったものなのか完全にはわかっていなかった」
ティップを繊細に仕上げるためのソリッドに、細身肉厚のチューブラーブランクはフルソリッドに近い操作性を獲得。だが、単純にスピニングロッドのガイドをベイト仕様へと載せ替えるだけでは竿として機能しない。ひとことで言えばバットの存在を強調することで、ハーミットは形作られていったという。
2020年に『STEEZ AIR TW』へと乗り換えた川口は、次なる野望を抱いた。
「とにかくキャストが決まる。かつてよりさらに極まった。そこに新たなるロッドの性能が加われば、より小技が利いて無敵のベイトフィネスが期待できる」
9年の歳月を経て、2021年に2代目STEEZハーミットC64L-SV・STが産声を上げることになった。今季26年には、さらに3代目となるSTEEZハーミットC64UL-ST・BFへと生まれ変わる。
「何より新モデルを開発するごとにDAIWAのテクノロジーが劇的に進化していくのに驚いた。ボトムでのタッチ感度はもちろんのこと、中層の釣り、特にミドストをやって、どこを引いてきているのか、どのレンジにいるのかが明確にわかる。水押しでの感度が伝わるなんて、そんな時代が来たのもDAIWAの技術力のおかげ」
かつては手探りの感があった中層の釣りが手に取るようにかわる千里眼コンセプトを採用。ミドストの名手・川口の釣りが誰にでも体感できる時代がついに訪れたのだ。
2025年以降、全国ツアーをトレイルするJBトップ50から、霞ヶ浦〜利根川の広大な水域を舞台とするMLF Japanへと主戦場を移した川口。STEEZハーミットとSTEEZ AIR TW、そしてSTEEZネコストレート、その出番は以前よりもさらに登板回数を増やしつつあるという。
川口のデッキから、今なおベイトフィネス・スペシャルコンボ・三種の神器が消えることはない。